前回(資本論を「ちゃんと」読むにあたり)のつづき

もう一つマルクス 資本論の哲学 (岩波新書) | 熊野 純彦 から

一枚目の図、こういう図を見てみたかった!商品が持ち主を変える図!生産から流通、消費に移る、分かりやすい!
この図にないのは財政支出と税、ということになりますね。
貨幣の生産と消費?
次元を増やす感じ?垂直方向に貨幣の生産と消費の軸が追加されるイメージですかね。
サーキットセオリーという考え方がそれです
サーキットセオリー(^^)初めて聞く言葉です。
MMTの手法として紹介されてました

新たな財政再建不要論:現代貨幣理論(MMT)
このセンセイの文はネタに使えるかも。
【MMTの貨幣論】
このように考えるのは、彼らが、主流派経済学が想定してきたものとは異なる貨幣論に立脚していることが大きく影響しています。主流派経済学は、貨幣の起源を物々交換が直面する「二重の欲望」という困難性を克服するために登場した「一般的受容性」に求めます。これは金属主義(Metallism)と呼ばれている立場です。これに対して、MMTは、貨幣の起源を、政府が発行し、それによって納税することを要求することに求めています。これは表券主義(Chartalism)と呼ばれている考え方です。このため、MMTは、しばしば新表券主義(Neo-Chartalism)とも呼ばれています。
この引用箇所、どう思いますか?
二重の欲望、とか一般的受容性とか小難しい言葉が満載で一読して意味が分かりません。
表券主義ということばは聞いたことがあります、nyunさんのブログで
一般的受容性ってもしかして、皆が価値があると思っているから貨幣は流通するという考えかなぁ。
ダメだなあと思うの「これに対して」というレトリックなんです。
金属主義というのと表券主義が対立するように扱っているからですか?
このバカが言う「一般受容性」というやつがあるものを政府が発行して納税させているという考えは、どちらに入りますかね?
両方?
そうなりますよね
なるほど
「一つに過ぎないものを分けて考えてしまう。」
スピノザ?!
まあこれはとてもよくあるバカな論法なのですが、「MMTは表券主義である」というようにそれ自体は間違いとは言い切れない小さな真実をあげつらうことによって、それとは「金属主義」なるものの「一般的受容性」を軽視しているかのようなウソをいうわけです。
マルクスだって、むしろ「信用貨幣」をちゃんと論じたほとんど最初の人の一人であるにもかかわらず「金属主義」の仲間に入れられてしまうとか。
ほんとうに学者ってバカしかいないのかな?と思ってしまうわけです。
資本論で言えば、金なり銀なりの硬貨が紙幣になり、それは記号なのだということがちゃんと書いてありますよね。その同じ考えは現代の電子マネーにも展開できるわけですよ。
そのように考えるためのとりかかりとして、熊野さんのこの図を発展させていけばいい

流通の媒介者としての姿では、金は、ありとあらゆる侮辱をこうむり、けずりとられ、そしてただの象徴的な紙切れになるまでうすくされさえした。だが貨幣としては、これにその金色の栄光がかえしあたえられる。それは奴僕から主人になる。それはただの下働きから諸商品の神となるのである。
「経済学批判」岩波文庫 p160
諸商品の交換価値がその交換過程をつうじて金貨に結晶するように、金貨は通流のなかで自分自身の象徴に昇華し、まず摩滅した金鋳貨の形態をとり、つぎには補助金属鋳貨の形態をとり、そしてついには無価値な徴票の、紙券の、つまり単なる価値表章の形態をとるのである。
同 p147
そうですね。
そして、資本論の交換過程の記述は、熊野や佐々木のような「図」を思わず書きたくなるんです。
図を描きたくなると言うとMMTもそうで、こんなのを描いていたことを懐かしく思い出します。

懐かしい(^^)これで勉強しました!
ん?
どこが似ているかと言うと、経済をインプットとアウトプットがあるシステムとして、まるっと把握しようとするホーリスティックなビューなんですね。
系、つまりシステム思考なんです。
生態系もまた「系」ですから。熊野さんの図を見て、資本論の前半を読み直してますますそう思えてきました。
そして、貨幣や商品を「記号」と見る考え方。これも新しい。
昨今流行りのグラフ理論を先取りしている感じがします。
対して経済学の考え方は、結局のところ、こうなんです。

あるいはせいぜい、こう

ここには法則がない
経済学者は、だから好きなことが言える
それぞれの「記号」が独立しているものとして解釈していいなら、解釈は無限に作れてしまいます。
なるほど
なのだけど、マルクスが新しいのはこういう感じで

システムに入ったWは必ず等価なGとつながっているとか、システムから出ていくWの前には必ず等価なGがある、みたいな。
あと。。。
「誰かの売りは誰かの買いである」
「システムを循環する金貨の量は、出入りがない限り不変」
こうした絶対事実から論理的な推論を組み立てていくのは、まさにグラフ理論的なんですよね。
なるほど〜

MMTは「民間(非政府部門)の純金融資産は、政府の累積財政赤字である」という絶対事実を出発点の一つとしますけれど、考え方が全く同じなんですよ。
現代のわれわれは、すでに整理されている「グラフ理論」などを知っているのでマルクスの文を「なるほどそういう感じか!」と理解することができるわけですが、先端を行き過ぎていると、読者が付いていけない。
マルクス自身、表現に苦心したはずなんです。
だからわれわれはマルクスを読むときは、「いつもシステムで考えている人なんだ」という意識を手放さないことが肝要だと思います。これはMMTも同じですね。
それは石倉先生が言われる「オリジナルの議論を、どこまで「一貫したもの」と把握できるのかを考え抜く態度」と同じものだと思います。
だからマルクスの言いたかったことを視覚化していくという作業が重要になるのですね
そういうことになりますね
視覚というか、幾何的な把握?
ここは本当にスピノザと通じるところがあります。
スピノザと幾何的な把握はどのように通じますか?
そもそもエチカはユークリッドの「原論」の形式で書かれているわけで。。。
それはおいおいやりましょう(笑)
かるちゃんはフーリエ変換習いました?
習ってないです
ではNMR分析は?
分子構造を解析する核磁気共鳴
学生時代にやった気がします
なんかスペクトルを解読する

それです!
たとえば純粋なエタノールだと、こういうスペクトルが観察される

今となってはなんでこうなるのか思い出せない…でも勉強した記憶はあります
このスペクトルは、もとの測定データをフーリエ変換して見やすくしたやつなんですね。変換する前のFID信号を見ても人間には何が何だかわからない。

へぇ〜
これは、同じものの「見方」を変えているだけなんです。
こういうイメージ

おおー
「時間領域を周波数領域に変換する」というのはこういうことなんですね
これがフーリエ変換!
これはフーリエ変換の一つの実用例、というわけです。
変換の本質は、あらゆる曲線は正弦波の重ね合わせで表現できる!ということでしょうね。

昔NHKのテレビでこういうのやってて見た記憶が。
上のNMRは典型的だと思いますけれど、マルクスにも見られるのは「視点」をガラリと変えて、もういちど全体を把握し直すという思考ですね。
なるほど
そうすると、「一見したところ○○」なものがぜんぜん別の相貌で「現れる」。
現代で言うと、国債は「一見したところ」財源のためということになっている。
しかし!
こうやって「見る」と、国債のグロテスクな談合構造がありありと見えるわけです。
NMRはまさにそうなのですが、見方を変えて、見やすくしてからさらに細かく「見る」のですね。
たとえば、この黄色く囲ったあたりを特に「よく見る」とか
そうですね
それが科学ですよね!
ですね(^o^)
だから「主流経済学は○○観でありマルクスなりMMTは××観である」みたいな主張は、バカな非科学的妄想にしか見えないんですよ。
わざわざ一番わかりにくいビューのままで、それぞれが勝手に好きな物語をでっちあげる。
それがまっとうな議論と言えますか?
わんわんわんわんわわんわんわ
ニュんさんのスイッチが(^o^)
マルクスのデビュー作「哲学の貧困」もそうですが、「資本論」でも「経済学は自分でわざわざそのように観察したものを、自分が発見したかのように説明する」というような批判をしていて、そんな箇所に出会うと楽しくなりますね。

GとWの話に戻ると、Wの移動を「持ち主が変わった」と把握しますよね。これはとても現代的だと思います。
この図、持ち主を書いたらもっと分かりやすいのになと思ったり

わたくしもちょっと描いてみましょう

マルクスって、こういう「状態変化」的な把握をしてますよね。
ふむふむ
現代のわれわれはこういう思考に慣れているので、次のこの図にもついていけると思います。
どうですか?

Aさんが商品Wを所有していて、Bさんに4千で売った?
これはグラフ理論的な表記です。
紙幣は「記号」であり、それは当然「誰かが持っているものである」と気づいていたマルクスは、ほとんどこの理解に到達していたわけです。だから、最初からそう考えて読むべきだと思うんでよね。
「オリジナルの議論を、どこまで「一貫したもの」と把握できるのかを考え抜く」
(石倉雅男先生)
なるほど
というわけで思考を進めましょう。わたくしたちの理解では、IOUも商品でしたよね。
だからこれも理解できる

AさんがIOUを発行して、Bさんから4000受け取った
ん-
そうではなくてこのIOUは「債務証書」のつもりです。
上のAさんは「誰かの債務証書」を持っていて、それをBさんに4000で売ったことの描写です。
なるほど
資本論の交換過程のところで、リンネル織布者さんは、まず手持ちのリンネルを市場に持ち込んで2ポンド金貨を手に入れます。

はい
こうも書けます

ふむふむ
次に、その金貨で別の人から聖書を買います。
こうでしょうか

リンネル織布者さんが聖書を買いました
これからここでは、資本論をこんな感覚で読んでみようと思うんです。
マルの中の下の数字はその人の「正味のお金」ですが、マルクスが単に「お金」と言ったときに、それはこの「正味のお金」なのか、それとも「金貨」なのかをちゃんと区別するわけです。
商品としての金貨と、計算貨幣としての金貨みたいな感じですかね
好みとしては「計算貨幣」でなく「計算単位」かなあ。
とにかく図の通り(笑)
そう理解します
なるほど(^^)
図の実物側(上)と数字側(下)というか。
ふむふむ、理解できます
現代なら一般化して「(文字、数字)と表記する」とか言いそう
コンピュータのプログラミングとかでも
面白い(^^♪
ほんとに\(^o^)/
熊野さんの図は間違いじゃないけれど、つまらない
こちらはそれでいてちゃんと「系の中の金貨の量は不変」とか「数字の合計は不変」という真理を維持しているでしょう?
たしかに!
わたくしは最近、流体粒子のシミュレーションなんかもやるのですが、ほんと同じだなって思うんですよね。
粒子の性質をいくつかのパラメーターとして定義して、数字をぶち込んで、ランダムに衝突させたりするとか。
そんな、現代の工学の先端に近いところと同じ思考をマルクスはしてるぞ!としか思えない。
マルクスって天才なんだなぁ
シミュレーションで、粒子が動く「場」を考えなくてはいけないんですね。
重力場とか電場とか磁場とか。
マルクス理論では、それが mode of production 、生産様式にあたるという感じです。
なるほど
シミュレーションすると「国債をどんどん発行しましょう!」という立場をとる粒子のとこにはどんどん「数字」が集まる、みたいな。
多くの粒子は死ぬんですけどね。
(イメージです)
ひえ~( ゚Д゚)
(たぶん死ぬ粒子の側)
歴史的には矛盾に気づく粒子たちが団結して革命になるはず?
そうでないと、子供がかわいそすぎる( ;∀;)
結論からいうと「場の条件」として「生産手段の私有」を維持する限り、どうしても格差は拡大するんです。
ふむふむ
プルードン氏の言うようになるはずがない。それは法則に反しているわけで逆に悪いことが起こるか、せいぜい破滅の速度を落とすくらいで。
たとえ消費税が廃止になってもあんまり意味ないんです。
問題は生産様式、生産手段の私有にあると
というよりも、それが支配的な条件であることに多くの人が気づいていないことかなと。
たしかに、今の状態が当たり前すぎて、悪いことだと気づけないかも
経済学者のように変な思考をせずに科学的に考えるとJG以外にないと思われるんですよね
なんで反対する人がいるんか理解ができないんですよね
自分はなにも難しい事は分からないんですけど、さいしょ直観でJGいいと思ったんです。
具体例をだせとかオラついている人たちの気持ちが全然理解できないんです
なんで自分らの利益になること、権利の保障を恐れるのか
「異なる枠組みを前提にするMMTに対しては、これまでの財政再建否定論に対するのとは別の検討を必要とします。その理論的な起源にまで遡って、その議論を丁寧に吟味する必要があるように思います。」
だそうで
これはいったい
いまのは、上の 齋藤潤 センセイの締めの言葉ですが学者はこうなっちゃうわけですよ
「丁寧」だ????
わんわんわんわんんわんわんわんわん
わーにゅんさん落ち着いて~(^^)
資本論に戻りまかすか(笑
フーリエ変換ってMMTと似てるワンね。
「数字のほうのお金」は、預金とか現金とか、さまざまな IOU の重ね合わせである、とか。
確かに
本文を読み始める前にあと一回、今日説明した考え方でマルクスの「交換」を分析してみようと思いまーす
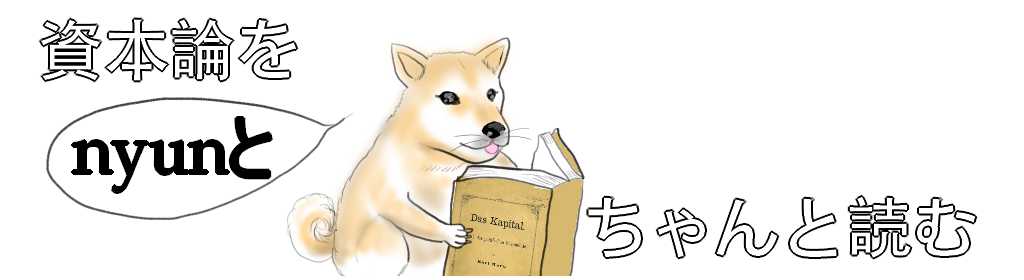


一枚目・二枚目の図は出典が逆では?
一枚目→佐々木氏、二枚目→熊野氏ですよね
>46さん
いけない!直しました。
どうもありがとうございます。
興味深い記事だと思いますが、一つ疑問があります。
それは石倉先生の「オリジナルの議論を、一貫したものと把握する」ということと、前の記事の石川先生の「マルクスを信用貨幣として読む」ことは真逆だということです。後者はマルクスの本意と離れて独自に解釈をしていると考えられます。
マルクスは信用貨幣についても述べていますが、1篇2章(岩波版だと第一巻165頁)に「金*は、それ自身の価値の大いさを、相対的に、他の商品で表現するほかない。それ自身の価値は、その生産に要した労働時間によって規定される。」(*貨幣としている版もある)と述べており、マルクス自身が資本論の体系において、労働価値説(商品貨幣論)と信用貨幣論という矛盾を抱えていると考えます。
これを矛盾のないように解釈するには、結局オリジナルをものを再構成して解釈し直すしかないと考えます。
これは岩井克人「貨幣論」に書かれている話で、ぜひそちらもご覧いただければ面白いと思います。