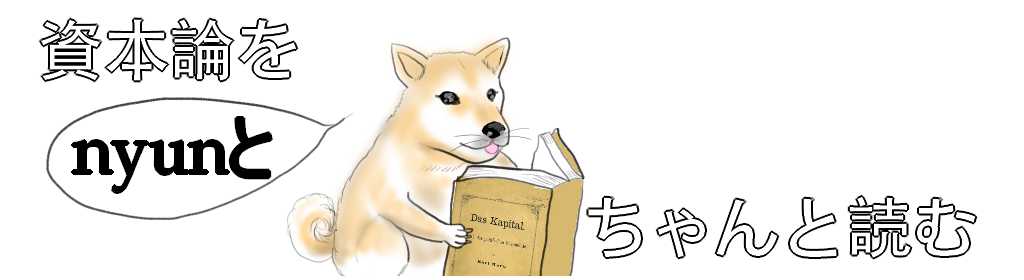〈1-2〉
1.Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgröße)
1.商品の2因子、すなわち使用価値と価値(価値実体と価値大いさ)
前回、「準備編1」と銘打って2があるかのような書き方をしたのだけれど。
資本論を nyun とちゃんと読むための準備編1 「実体」とは? – 資本論をnyunとちゃんと読む
そのあたりはブログに書いたから準備編はもういいか(笑)
「弁証法」と訳されるディアレクティークという方法について基礎的だけれども、理解されていなさそうなことについて書いているので。。。
よろしく!
それでは、じゃーん

これは。。。
Erstes Kapital (第一章)
Die Ware (商品)
1. Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgröße)
今回は、この太字部分の話をします。
高畠訳
商品の二因子、すなわち使用価値と価値(価値の実体と価値の大小)
向坂訳
商品の二要素 使用価値と価値(価値実体、価値の大いさ)
中山訳
商品の二つの要素:使用価値と価値(価値の実体、価値の大きさ)
大月書店
商品の二つの要因 使用価値と価値(価値実体 価値量)
とりあえず、この節タイトルを少し分析しましょう。
「商品の二つのファクター:使用価値と価値(価値の実体、価値の大小)」
(とりあえず nyun 訳)
はい
ファクターって何でしたっけ?
え
えっと
要素?
では要素とは?
難しい
そのものの性質を決めるもの?
そのように要素を考えるときには何らかの「そのもの」が考えられているはずです。
ファクターに対応するものとして”Das Ganze(ダス ガンツェ)”「全体」「総体」がある。
ファクターとは第一には、それを欠いたら「全体」ではなくなってしまう何かです。
なるほど
もうひとつファクターは複数あることが多くて、その場合、それは互いに排他なんです。
わかりますか?
質と量のように
質を考えるとき量は捨象され、量を考えるとき質は捨象されるのでしたね
そうですね。
ところで因数分解は英語で factorization ですが、たとえば「ある数 X をA×Bという排他的なファクターに分解する操作」ということです。
このときAとBは排他であり、なおかつ、どちらかを欠いたらXにはなりません。
こういうのがファクターというわけ。
なるほど
因数分解はイメージしやすいです。
ここでマルクスは「商品」を「使用価値」と「価値」の二要素に分解しているわけですが、このように、三つとか四つではなく、対極関係にある二要素に分解するのがヘーゲルの基本的な方法です。
はい
分解と逆に、その二要素を総合すると「全体」になります。
なるほど
さて、アリストテレスだったら商品の価値を「使用価値」と「交換価値」に分解するでしょう。
というか、そうしたと言えます。
【なぜならば、どの物にも二つの用途があるからである。――一方の用途はその物に固有なものであるが、他方の用途は固有ではない。たとえば、靴には、一方でははくという用途と、他方では交換品としての用途とがある。両方とも靴の使用価値である。というのは、靴を、自分の持っていないもの、たとえば食物と交換する人でも、やはり靴を靴として用いるのだからである。といっても、それは靴の固有な用い方ではない。なぜならば、靴は交換のために存在するのではないからである。アリストテレス「政治学」】
資本論第2章交換過程注39
これを、こう表現してみます。

簿記のT字勘定みたいワンね
実はこの表現、そこから思いついたのです。
簿記のあれは「左右の数字がバランスする」ことが前提になるという先入観があったのでMMTには使いやすいけれど資本論の表現としてどうかと思っていたのだけど。
思っていたのだけど、と
これは三位一体的な考え方とか、ヘーゲル的な思考を表現するのにぴったりじゃないか!と気づいたのです。
ヘーゲルの、有-無-成の「弁証法の始まり」をこんな風に表すといい感じ。

ふむふむ
(実はわかっていない)
ちょっと説明すると、、、
「有」と「無」はまったく別の、対極にあるものですよね
そりゃそうワン
しかし「純粋な有」を考え、また「純粋な無」を考えるとこの二つは全く同じものなんです。
ええ?
じゃあたとえば「純粋な犬という概念」を考えてみてください。
「犬が存在する」ということを突き詰めて考えるということです。
まあやってみて。
。。。
じゃあ次に「犬が純粋に存在しない」を考えてみて。
これは「犬が存在する」とまったく同じことを考えていることになる、ということがわかりませんか?
おお、確かに!
してみると「犬」とは「犬がいる(犬である)」と「犬がいない(犬ではない)」の両方を考えていくことに他ならない。
そのことによって「犬」という概念は更新されていくわけ。

うーん
まあ、慣れです。
マルクスがこのタイトルで、商品の「使用価値」と対立するものとして「交換価値」とは書かないのはなかなか味わい深いものがあります。
並べてみましょう。

ここでマルクスは、使用価値(左)と「使用価値ではない価値」(右)のことを言っているのですね。
つまり、こう。

ある商品を手に取ってみるとそこには「価格」がついているけれど、それは「使用価値」とは全く関係がない。
では何だろう?というわけですね。
「交換」を先に言いたくないわけかな。
わかってきたような。
「使用価値ではない方の価値」を ”因数分解” してみましょう。

ふむふむ
これを、上の式の「使用価値ではない価値」に「代入」します。

おぉ〜
まったくほれぼれします。
マルクスこそはヘーゲルの真の弟子ですねえ。
節タイトルの文「Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgröße」これを表に書き換えましょう。

これはしびれます。資本論を読んでて一番難儀するのが価値という言葉の使われ方とか整理の仕方だと思いました。この表は明快で美しいし、とても役に立ちます。
こういう三位一体の、巨大な入れ子構造が「確実な知の体系」つまり「科学そのもの」を成すわけです。
これからはこのT字表記を駆使することにしましょう。
自分もようやくこの方法にたどり着きました。
おぉ〜
タイトルの構造が読み取れれば難儀する必要は全くないんですよね。
そこがむつかしいと受け取られるとしたら、説明がよくないんです。
だってこれ以上なく明晰に、ありありと書いてある!
デカルト的な考えに見えます
そう感じる方にはヘーゲルの哲学史講義をお勧めしておきます。
あれ面白いから。
こういうのがいわゆるヘーゲル流の「論理」で、三段論法とは異なる論理だということを注意しておきましょうか。
うまく説明できないけれど、違うのです(笑
単なる要素還元とは何が違うのでしょうか?
「単なる要素還元」がちょっとピンと来ませんが、要素に還元するということは「ダス ガンツェ」がハッキリしていなくてはいけませんよね。
還元とは反対の、総合によって「ダス ガンツェ」が出来上がるという往復運動で把握するんです。
「犬」には「ワンと鳴く性質」などのファクターがあるけれど「非犬ではないもの」という全体的な把握も必要、ということとか。
あと「慣れ」も大事で、新しい思想は徐々に精神と浸透しあうんです。ヘーゲルがそんなことを言っていたと思います。
昨今のMMT的な考え方の「浸透」もぼくにはそういう感じに見えていて、だって「国債はただの政府預金調達にすぎない」みたいに言い出す人が出てきていたり。
本人は気づいていないけれど、そういうのは浸透なんですよね。
で、後から「MMTは別に新しくない」という感じで。かつての地動説の浸透もおんなじなんですよね。コペルニクスは別に新しくない!
こう言えるかな?
現代のぼくたちが今あたりまえに「単なる要素還元」と呼んでいる思考は、デカルト~ヘーゲル時代に確立していったものなんです。
と、ここまで考えるとすごく有意義なご質問でした。
ありがとうございます。
付け加えると、要素還元思考は原子論に行き着きますよね。マルクスがそこから出発している(学位論文)のはまことに一貫しているんです。
「ちゃんと読む」ではエピクロス思想とのかかわりもちゃんとお話しできたらいいな。。。
ちょっとMMT話もしほしいワン
そうですねえ。
MMTって、貨幣という視点を取るというより、マネタリーシステムを三位一体関係の集合体として把握していると言えるでしょう。
こんなん?

マルクスやMMTに対して「言葉の定義がない」という評価をする人がいるのだけれど、こういう総体的体系把握にとって「定義」は重要ではないんですよね。
そういうところも共通しています。
ドイツ語の科学は Wissen(知)-schaft(集合体)で、Wissenshaft です。
発展する三位一体の知の体系。
このくらいにしておこうかな…
そうだ、宇野について。
返す返すも惜しまれます。ぼくのこの説明なら「価値実体論」の意味がわかってもらえたと思うのだけど。
「価値実体」は「定義」したものじゃないんですよね。総体的な把握によって確かに見出されるもの…というわけ。
上の図のように。
なるほど
総体的な把握の意味、定義しない理由、少し理解できた気がします
慣れてきましたね。