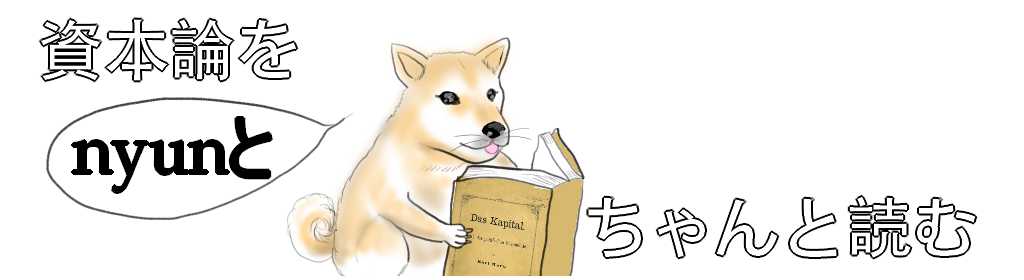前回のエントリにこんな感想をいただきました!

おお
自分も整理しました
マルクスは交換価値を定義せず、使用価値ではないナニカとすることで、商品の価値を全て網羅したんですね
一方、使用価値ではないナニカは、質と量という互いに直交する概念で全て網羅することができる
全てを網羅する方法は、少なくとも2種類の方法があることがここからわかります
もし交換価値を定義していたら、使用価値ではないナニカを全て網羅できず、抜け落ちるものが出てきます
何でもかんでも定義するやり方が良くないのはこの点なのですね
ただし、絶対に定義は良くないことを意味しているわけではない
使用価値は定義したものであって良い
つまり、いちど定義したならば、その定義に当てはまらないもの全体を考えなければ、全て網羅したことにならないという訳ですね
おお、ぼくの説明は成功していたようですね\(^o^)/
ここら辺は自信なかったんですけど大丈夫ですか?
「ただし、絶対に定義は良くないことを意味しているわけではない
使用価値は定義したものであって良い」
たとえば犬を定義するってよくわからないです
内包的でも外延的でも
「犬を定義する」とは考えたこともありませんでした。
どうすればいいんですか?
内包的なら共通の性質を示す、外延的なら列挙(ハスキー、芝犬、etc)
内包(Intension)はある概念がもつ共通な性質のことを指し、外延(extension)は具体的にどんなものがあるかを指すものである。これらは互いに対義語の関係をもつ。
Wikipedia 内包と外延
おっしゃりたいことがわかってきました。
ぼくにはこういうことと思われます。

「定義」というのは、この図の四角い枠線を引く行為のことのように思われます。
犬と、犬以外のものの間に線を引くということ言いたいわけワンね。
うん、ぼくのイメージで言うと弁証法的な思考はこんな感じ。

どのような場合に「犬ではない」のかを同時に考えつつ、あいまいな境界を決めていくとか、決まっていくという感じ?
だから内包的定義、外延的定義はどんどんやってくれてかまわない。
但し、カテゴリーは発展していくのです。
んーと?
このように書くこともできるでしょう。
内包も外延も、境界を決めていく運動だよね、みたいな。

なるほどねえ
T字表記は実に便利!
弁証法の論理は、定義から出発する推論の連鎖じゃないんです。三位一体の運動が展開し発展していく感じです。
よくマルクスの言葉は定義がなくてだんだん意味が変わる!と文句を言う人がいますが変わらない方がおかしいんですよ(笑