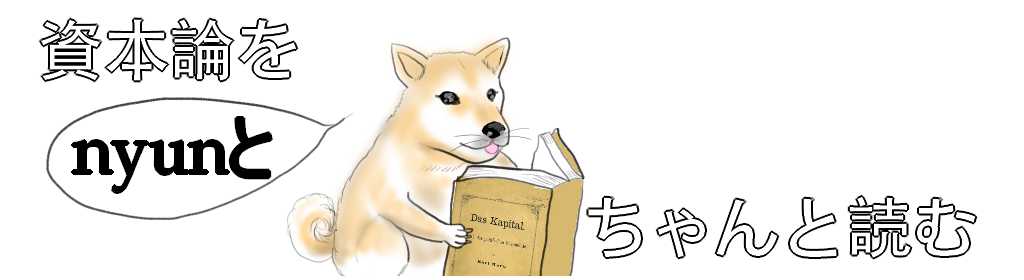note マガジン「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」で『「国定貨幣論」の本当の元祖、ニコラス・バーボンについて』という文章を書きました。
そこでバーボンの “A discourse concerning coining the new money lighter in answer to Mr. Lock’s Considerations about raising the value of money” (『より軽い新貨幣の鋳造に関する論究:ロック氏の貨幣の価値の引上げについての考察に答えて』)という、長いタイトルの小冊子を紹介し、その翻訳をしたいと書きました。
いろいろ探しましたが原文はこちらが読みやすいと思います。
さて、翻訳に関していくつか思うところがあります。ある程度の背景知識を前提にしないとまったく面白くないし、むしろ意味を取り違えるでしょう。それだとただ日本語に翻訳しても意味がない。
だって「より軽い新貨幣の鋳造」ってどういうこと?
その辺を確認しながら、まず序文(PREFACE)を読んでいこうと思うのですが、これはその第一回。
THIS Question, Whether it is for the Interest of England, at this time, to New-Coin their Clipt-Money, according to the Old Standard both for Weight and Fineness, or to Coin it somewhat Lighter? has been, of late, the business of the Press, and the common subject of Debate.
翻訳
この問題は、イギリスの利益のために、今、すり減った硬貨(Clipt Money)を鋳造し直す際に、重量と精度の旧基準に従うのか、それとも幾分軽く鋳造するかということです。これは、ここ数年、報道されることが多く、よくある議論のテーマです。
さて、いったいどのような大問題が?
楊枝嗣朗の「ロック=ラウンズ論争再論―イマジナリー・マネーとしてのポンドの観点より―」という論文から少し引用します。
”盗削著しい銀貨の改鋳が最終的には,従来の鋳造価格で実施されることが決定されたのであるから,1696年末から1700年にかけて改鋳された510万ポンドもの銀貨が,造幣局から送り出されるや否や消え
去る運命にあったことは,以下の1696年の小冊子からも推測しうるように,当時の識者や実務家には常識であった。”
通貨問題の話
英国の銀貨が、作っても作っても消失してしまい(海を渡ってフランスやオランダに渡ってしまい)英国の人々が日々の決済に困るという事態が起こっていたのです。
と同時に、英国はフランスとの戦争(英仏第二次百年戦争)の戦費がかさんだことで大増税と、巨額の国債発行を余儀なくされていました。
税を集めても、入ってくるのは質の悪い貨幣ばかり。
この辺りの事情はトマス・レヴェンソン著「ニュートンと贋金づくり」というノンフィクションにも生き生きと描かれています。
この本でレヴィンソンは、ヴィクトリア時代の歴史家マコーリー卿の報告をいくつか紹介しています。
危機が極限に達するころには、国庫に入る歳入一〇〇ポンドのうち、まともなシリング硬貨は一〇枚程度しかなかった--二〇〇〇枚に一枚の割合だ。マコーリー卿は「膨大な量が融解され、膨大な量が輸出され、膨大な量が貯め込まれたが、商品の現金箱にも農夫が家畜を売った代金を家に持ち帰る革袋にも、新しい硬貨はほとんどなかった」と書いている。
「わずか一年の間に劣悪なクラウンと劣悪なシリングによってもたらされた不幸は、四半世紀の間に劣悪な王、劣悪な大臣、劣悪な判事によってイングランドの国家が被ったあらゆる不幸に匹敵するのではないか」
「ホイッグとトーリーのどちらがよいか、プロテスタントとイエズス会のどちらが優っているかなどということはどうでもよく、牧畜業者は家畜を市場に運び込み、食料雑貨商はスグリの実を割り分け、服地屋はブロードを裁断し、買い手も売り手もそれまでと変わらずうるさく声を上げていた。」
「取引の主要は手段が完全に混乱してしまうと、すべての商売、すべての産業が打撃を受け、麻痺したようになった。害は日々常在し、あらゆる場所、あらゆる階層に及んでいた。」
通貨流出の理由
さて、英国から銀通貨が流失した理由は明白です。
それは、大陸にそれを銀地金として売れば、もっと高く売れたから。
つまり、地金の銀を融解して製造された硬貨の額面価格が、大陸における銀の価格よりも安かったからに他なりません。削り取りが横行したのもこのためで、手に入った銀貨のふちを少し削って売ればちょっとした儲けにつながりました。
バーボンのタイトルにある Coin it somewhat Lighter?、つまり「少し軽く鋳造してはどうか」という考えは、こうした状況に対応する一案として浮上したもので、硬貨に含まれる純銀の割合を減らせばいいのでは?という論理です。
たとえば額面はそのままだけど、銀の含有量は少ないよ、という感じの。
ロックに挑戦するバーボンという構図
さてバーボンの本ですが、次の三部構成になっています。
- 序文
- ロック氏の本の内容、もしくは主な主張
- より軽い新貨幣の鋳造に関する論究 富、および諸事物の価値について
このようにバーボンは、相手の主張を整理してから、それに反論を加えていくという形式を踏んでいるのです。
だからまずはそこまでの部分を理解しないとつまらない。翻訳を序文から始めようと思ったのはそんな動機です。
そしてロックとバーボンの論理を通じて、それを踏まえたマルクスの論理を深く理解していこうではありませんか。
そんな風に思っています。
ついでに、MMTとこの時代
最後に、別のエントリ(対話篇:だから貨幣の前に価格を見よ)でも触れたのですがMMTの新しい本(未翻訳)にこの時代に関する論考がありまして、ちょっとびっくりしたのです。
“Credit and the Exchequer since the Restoration”、王政復古以降の信用と財政というこの小論では、この時代の決済ぶりを別の角度から論じたもので、決済貨幣が不足したその時に、それゆえにこそタリー(信用と借用書のペアのようなもの)を用いた決済が急発達したさまが描かれています。
ちなみに筆者のRichard Tye さんは参考文献としてこちらを挙げていたりします。
いつの日かTyeさんの論文もご紹介したいのですが、まずはバーボンですよね(笑
次回は序文は最後まで行ける、、、かな