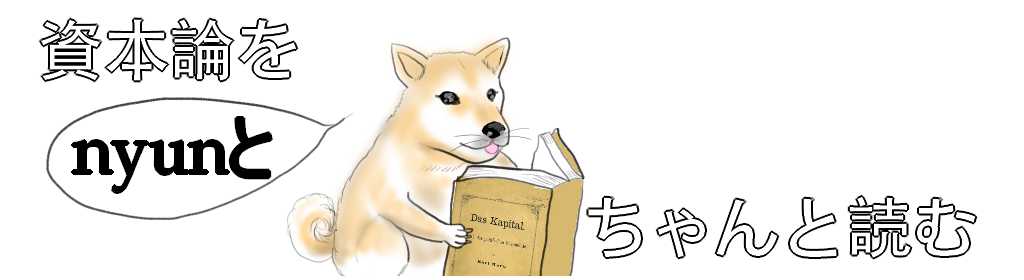<1-2>「商品の二つのファクター」とは?
〈1-2〉
1.Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgröße)
1.商品の2因子、すなわち使用価値と価値(価値実体と価値大いさ)
前回、「準備編1」と銘打って2があるかのような書き方をしたのだけれど。
資本論を nyun とちゃんと読むための準備編1 「実体」とは? – 資本論をnyunとちゃんと読む
そのあたりはブログに書いたから準備編はもういいか(笑)
「弁証法」と訳されるディアレクティークという方法について基礎的だけれども、理解されていなさそうなことについて書いているので。。。
よろしく!
それでは、じゃーん

これは。。。
Erstes Kapital (第一章)
Die Ware (商品)
1. Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgröße)
今回は、この太字部分の話をします。
高畠訳
商品の二因子、すなわち使用価値と価値(価値の実体と価値の大小)
向坂訳
商品の二要素 使用価値と価値(価値実体、価値の大いさ)
中山訳
商品の二つの要素:使用価値と価値(価値の実体、価値の大きさ)
大月書店
商品の二つの要因 使用価値と価値(価値実体 価値量)
とりあえず、この節タイトルを少し分析しましょう。
「商品の二つのファクター:使用価値と価値(価値の実体、価値の大小)」
(とりあえず nyun 訳)
はい
ファクターって何でしたっけ?
え
えっと
要素?
では要素とは?
難しい
そのものの性質を決めるもの?
そのように要素を考えるときには何らかの「そのもの」が考えられているはずです。
ファクターに対応するものとして”Das Ganze(ダス ガンツェ)”「全体」「総体」がある。
ファクターとは第一には、それを欠いたら「全体」ではなくなってしまう何かです。
なるほど
もうひとつファクターは複数あることが多くて、その場合、それは互いに排他なんです。
わかりますか?
質と量のように
質を考えるとき量は捨象され、量を考えるとき質は捨象されるのでしたね
そうですね。
ところで因数分解は英語で factorization ですが、たとえば「ある数 X をA×Bという排他的なファクターに分解する操作」ということです。
このときAとBは排他であり、なおかつ、どちらかを欠いたらXにはなりません。
こういうのがファクターというわけ。
なるほど
因数分解はイメージしやすいです。
ここでマルクスは「商品」を「使用価値」と「価値」の二要素に分解しているわけですが、このように、三つとか四つではなく、対極関係にある二要素に分解するのがヘーゲルの基本的な方法です。
はい
分解と逆に、その二要素を総合すると「全体」になります。
なるほど
さて、アリストテレスだったら商品の価値を「使用価値」と「交換価値」に分解するでしょう。
というか、そうしたと言えます。
【なぜならば、どの物にも二つの用途があるからである。――一方の用途はその物に固有なものであるが、他方の用途は固有ではない。たとえば、靴には、一方でははくという用途と、他方では交換品としての用途とがある。両方とも靴の使用価値である。というのは、靴を、自分の持っていないもの、たとえば食物と交換する人でも、やはり靴を靴として用いるのだからである。といっても、それは靴の固有な用い方ではない。なぜならば、靴は交換のために存在するのではないからである。アリストテレス「政治学」】
資本論第2章交換過程注39
これを、こう表現してみます。

簿記のT字勘定みたいワンね
実はこの表現、そこから思いついたのです。
簿記のあれは「左右の数字がバランスする」ことが前提になるという先入観があったのでMMTには使いやすいけれど資本論の表現としてどうかと思っていたのだけど。
思っていたのだけど、と
これは三位一体的な考え方とか、ヘーゲル的な思考を表現するのにぴったりじゃないか!と気づいたのです。
ヘーゲルの、有-無-成の「弁証法の始まり」をこんな風に表すといい感じ。

ふむふむ
(実はわかっていない)
ちょっと説明すると、、、
「有」と「無」はまったく別の、対極にあるものですよね
そりゃそうワン
しかし「純粋な有」を考え、また「純粋な無」を考えるとこの二つは全く同じものなんです。
ええ?
じゃあたとえば「純粋な犬という概念」を考えてみてください。
「犬が存在する」ということを突き詰めて考えるということです。
まあやってみて。
。。。
じゃあ次に「犬が純粋に存在しない」を考えてみて。
これは「犬が存在する」とまったく同じことを考えていることになる、ということがわかりませんか?
おお、確かに!
してみると「犬」とは「犬がいる(犬である)」と「犬がいない(犬ではない)」の両方を考えていくことに他ならない。
そのことによって「犬」という概念は更新されていくわけ。

うーん
まあ、慣れです。
マルクスがこのタイトルで、商品の「使用価値」と対立するものとして「交換価値」とは書かないのはなかなか味わい深いものがあります。
並べてみましょう。

ここでマルクスは、使用価値(左)と「使用価値ではない価値」(右)のことを言っているのですね。
つまり、こう。

ある商品を手に取ってみるとそこには「価格」がついているけれど、それは「使用価値」とは全く関係がない。
では何だろう?というわけですね。
「交換」を先に言いたくないわけかな。
わかってきたような。
「使用価値ではない方の価値」を ”因数分解” してみましょう。

ふむふむ
これを、上の式の「使用価値ではない価値」に「代入」します。

おぉ〜
まったくほれぼれします。
マルクスこそはヘーゲルの真の弟子ですねえ。
節タイトルの文「Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgröße」これを表に書き換えましょう。

これはしびれます。資本論を読んでて一番難儀するのが価値という言葉の使われ方とか整理の仕方だと思いました。この表は明快で美しいし、とても役に立ちます。
こういう三位一体の、巨大な入れ子構造が「確実な知の体系」つまり「科学そのもの」を成すわけです。
これからはこのT字表記を駆使することにしましょう。
自分もようやくこの方法にたどり着きました。
おぉ〜
タイトルの構造が読み取れれば難儀する必要は全くないんですよね。
そこがむつかしいと受け取られるとしたら、説明がよくないんです。
だってこれ以上なく明晰に、ありありと書いてある!
デカルト的な考えに見えます
そう感じる方にはヘーゲルの哲学史講義をお勧めしておきます。
あれ面白いから。
こういうのがいわゆるヘーゲル流の「論理」で、三段論法とは異なる論理だということを注意しておきましょうか。
うまく説明できないけれど、違うのです(笑
単なる要素還元とは何が違うのでしょうか?
「単なる要素還元」がちょっとピンと来ませんが、要素に還元するということは「ダス ガンツェ」がハッキリしていなくてはいけませんよね。
還元とは反対の、総合によって「ダス ガンツェ」が出来上がるという往復運動で把握するんです。
「犬」には「ワンと鳴く性質」などのファクターがあるけれど「非犬ではないもの」という全体的な把握も必要、ということとか。
あと「慣れ」も大事で、新しい思想は徐々に精神と浸透しあうんです。ヘーゲルがそんなことを言っていたと思います。
昨今のMMT的な考え方の「浸透」もぼくにはそういう感じに見えていて、だって「国債はただの政府預金調達にすぎない」みたいに言い出す人が出てきていたり。
本人は気づいていないけれど、そういうのは浸透なんですよね。
で、後から「MMTは別に新しくない」という感じで。かつての地動説の浸透もおんなじなんですよね。コペルニクスは別に新しくない!
こう言えるかな?
現代のぼくたちが今あたりまえに「単なる要素還元」と呼んでいる思考は、デカルト~ヘーゲル時代に確立していったものなんです。
と、ここまで考えるとすごく有意義なご質問でした。
ありがとうございます。
付け加えると、要素還元思考は原子論に行き着きますよね。マルクスがそこから出発している(学位論文)のはまことに一貫しているんです。
「ちゃんと読む」ではエピクロス思想とのかかわりもちゃんとお話しできたらいいな。。。
ちょっとMMT話もしほしいワン
そうですねえ。
MMTって、貨幣という視点を取るというより、マネタリーシステムを三位一体関係の集合体として把握していると言えるでしょう。
こんなん?

マルクスやMMTに対して「言葉の定義がない」という評価をする人がいるのだけれど、こういう総体的体系把握にとって「定義」は重要ではないんですよね。
そういうところも共通しています。
ドイツ語の科学は Wissen(知)-schaft(集合体)で、Wissenshaft です。
発展する三位一体の知の体系。
このくらいにしておこうかな…
そうだ、宇野について。
返す返すも惜しまれます。ぼくのこの説明なら「価値実体論」の意味がわかってもらえたと思うのだけど。
「価値実体」は「定義」したものじゃないんですよね。総体的な把握によって確かに見出されるもの…というわけ。
上の図のように。
なるほど
総体的な把握の意味、定義しない理由、少し理解できた気がします
慣れてきましたね。
資本論第一巻(第二版)を読む
翻訳の方針等の説明
もう一つのサブコンテンツ「資本論-MMT-ヘーゲルを三位一体で語る」
「資本論をnyunとちゃんと読む」の構造
対話:「実体」概念に関して
本文
〈1-1〉
Erstes Kapital
Die Ware
第一章
商品
〈1-2〉
1.Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgröße)
1.商品の2因子、すなわち使用価値と価値(価値実体と価値大いさ)

〈1-3〉
[49] Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine “ungeheure Warensammlung” (1), die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.
(1) Karl Marx, “Zur Kritik der Politischen Ökonomie”, Berlin 1859, pag. 3. <Siehe Band 13, S. 15>
資本制生産様式が支配的である社会(複数)では、富は『商品の膨大なる集積」(一)として現れ、個別の商品がその要素形態として表れている。だから我々の研究は商品の分析から始まる。
*(一)カール・マルクス『経済学批判』(べルリン、一八九五年刊、第四頁)。
〈1-4〉
Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche -Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache (2). Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d.h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel.
(2) Verlangen schließt Bedürfnis ein; es ist der Appetit des Geistes, und so natürlich wie Hunger für den Körper … die meisten (Dinge) haben ihren Wert daher, daß sie Bedürfnisse des Geistes befriedigen.” (Nicholas Barbon, “A Discourse on coining the new money lighter. In answer to Mr. Locke’s Considerations etc.”, London 1696, p. 2, 3.)
商品はまずもって外界の一対象(Gegenstand)であり、その諸性質によって人類の何らかの種類の欲望を満たす物体(Ding)である。この欲望の本性(Natur)、つまりそれが胃袋から生じるものか、あるいは空想から生じるかは、ここでの分析に何等影響するものではない(二)。また、その物体がどのようにして人類の欲望を満たすものであるか、つまり直接的に生活の手段(Mittel)つまり享楽の対象としてであっても、もしくは間接的に生産の手段(Mittel)としてであっても、その違いはここの分析には影響しない。
*(二)『願望は欲望を含む。それは心の食欲であって、身体に於ける飢えのように自然的のものである。・・・・大多数は心の欲望を充たすことによって価値を受けるのである』ニコラス・バーボン著『新貨軽鋳論、ロック氏の貨幣価値引上論考に答う』ロンドン、一六九六年刊、第二及び三頁)。
〈1-4〉精読
ニコラス・バーボンについて
「外界の一対象(Gegenstand)」について
〈1-5〉
Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier usw., ist unter doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität. Jedes solches Ding ist ein Ganzes vieler Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen[49] Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken ist geschichtliche Tat. (3) So die Findung gesellschaftlicher Maße für die Quantität der nützlichen Dinge. Die Verschiedenheit der Warenmaße entspringt teils aus der verschiedenen Natur der zu messenden Gegenstände, teils aus Konvention.
(3) “Dinge haben einen intrinsick vertue” (dies bei Barbon die spezifische Bezeichnung für Gebrauchswert), “der überall gleich ist, so wie der des Magnets, Eisen anzuziehen” (l.c.p. 6). Die Eigenschaft des Magnets, Eisen anzuziehn, wurde erst nützlich, sobald man vermittelst derselben die magnetische Polarität entdeckt hatte.
鉄や紙など、それぞれ有用な物体は、二重の(doppelt)観点、つまり質と量との両面から考察される。こうした有用な物体はどれも、多くの性質がまとまった一全体(ein Ganze)であり、だからさまざまな方面に有用ということになる。これら物体のさまざまな方面の諸用途は、人類がその都度発見してきたものである(三)。有用物体の分量の社会的な公認尺度(Maß)もまたその都度決められてきたものである。商品の量を測る尺度にはさまざまなものがあるが、それは秤量される対象(Gegenstand)の本性(Natur)が多種多様であるためであり、あるいは慣習でそうなった部分もある。
*(三)「諸物は内的な効力(intrinsick vertue、これはバーボン特有の使用価値を意味する言葉である)を持っている。すなわち、どこにあっても同じ効力を持っている。たとえば磁石は鉄を引き付けるというように。」(同前、第六頁)
磁石が鉄を引きつけるという性質は、その性質自体(derselben)を通じて人が磁極性を発見して初めて有用になったのである。
〈1-6〉
Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert (4). Aber diese Nützlichkeit schwebt nicht in der Luft. Durch die Eigenschaften des Warenkörpers bedingt, existiert sie nicht ohne denselben. Der Warenkörper selbst, wie Eisen, Weizen, Diamant usw., ist daher ein Gebrauchswert oder Gut. Dieser sein Charakter hängt nicht davon ab, ob die Aneignung seiner Gebrauchseigenschaften dem Menschen viel oder wenig Arbeit kostet. Bei Betrachtung der Gebrauchswerte wird stets ihre quantitative Bestimmtheit vorausgesetzt, wie Dutzend Uhren, Elle Leinwand, Tonne Eisen usw. Die Gebrauchswerte der Waren liefern das Material einer eignen Disziplin, der Warenkunde (5). Der Gebrauchswert verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Konsumtion. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des – Tauschwerts.
(4) “Der natürliche worth jedes Dinges besteht in seiner Eignung, die notwendigen Bedürfnisse zu befriedigen oder den Annehmlichkeiten des menschlichen Lebens zu dienen.” (John Locke, “Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest”, 1691, in “Works”, edit. Lond. 1777, v. II, p. 28.) Im 17. Jahrhundert finden wir noch häufig bei englischen Schriftstellen “Worth” für Gebrauchswert und “Value” für Tauschwert, ganz im Geist einer Sprache, die es liebt, die unmittelbare Sache germanisch und die reflektierte Sache romanisch auszudrücken.
(5) In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht die fictio juris, daß jeder Mensch als Warenkäufer eine enzyklopädische Warenkenntnis besitzt.
物体が使用価値になるのはその有用性によってである(四)。但しこの有用性は宙に浮かんでいるのではない。この有用性は、商品体(Warenkörper)の諸性質を前提としており、それ(商品体)そのもの(denselben)を抜きに存在するものではない。それゆえ、鉄や小麦やダイヤモンドなどという商品体そのものが使用価値または財である。商品体のこのような性格は、その使用に資する諸性質の取得が人間に費やさせるところの労働の多少にはかかわりがない。使用価値を考察する際には、一ダースの時計とか一エレの亜麻布とカ一トンの鉄などのような、その量的な規定性が常に前提とされている。諸々の商品の諸々の使用価値は、一つの独自な学科である商品学の材料を提供する(五)。諸々の使用価値は、ただ使用または消費によってのみ実現される。諸々の使用価値は、富の社会的な形式がどんなものであるかにかかわりなく、富の素材的な内容をなしている。我々によって考察されねばならない社会形式においては、諸々の使用価値は同時に、素材的な担い手になっている。交換価値の担い手に。
*(四)「諸物の自然的な価値(natural worth)は、さまざまな欲望を満足させたり人間の生活に役立つなどの適性にある。」(ジョン・ロック, “利子引き下げがもたらす帰結についての諸考察(Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest)”, 1691, in “Works”, edit. Lond. 1777, v. II, p. 28.)
17世紀になっても英語の文章にはしばしば、Worthを使用価値、Valueを交換価値として表している例がしばしば登場するが、これはまったく、直接的な事柄をゲルマン語で表現し、反射された事柄をローマ語で表現することを好む言語の精神によるものである。
*(五)ブルジョア社会では、商品の買い手であるすべての人が、商品に関する百科全書的な知識を持っているという法的擬制(fictio juris)が当然のこととなっている。
〈1-7〉
Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen (6), ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwert scheint daher etwas Zufälliges und rein Rela- <51> tives, ein der Ware innerlicher, immanenter Tauschwert (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto (7). Betrachten wir die Sache näher.
(6) “Der Wert besteht in dem Tauschverhältnis, das zwischen einem Ding und einem anderen, zwischen der Menge eines Erzeugnisses und der eines anderen besteht.” (Le Trosne, “De l’Intérêt Social”, [in] “Physiocrates”, éd. Daire, Paris 1846, p. 889.)
(7) “Nichts kann einen inneren Tauschwert haben” (N. Barbon, l.c.p. 6), oder wie Butler sagt:
“Der Wert eines Dings ist grade so viel, wie es einbringen wird.”
交換価値は、まずもって量の関係、すなわち、ある「使用価値の一束」が別の「使用価値の一束」と交換される割合として現れる(六)。こうした量の関係は、時間や場所によって絶えず変化する。このため交換価値は、偶然的で純粋に相対的なものでありながら、商品の内的で内在的な価値(valeur intrinsèque)であるという形容矛盾(eine contradictio in adjecto)に見える(七)。この問題をもっと詳しく見てみよう。
*(六)“価値とは、あるモノと別のあるモノとの間に存在する交換関係、ある製品の量と別の製品の量との間に存在する交換関係で成り立っている。” (ル・トローヌ, “社会の利益”, [in] “Physiocrates”, éd. Daire, Paris 1846, p. 889.)
*(七)“内なる交換価値を持つ物は存在しえない” (N. バーボン, 前掲書 6), もしくはバトラーがこう言ったように。”モノの価値は、それがもたらすものと同じだけである。”
〈1-8〉
Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen z.B. tauscht, sich mit x Stiefelwichse oder mit y Seide oder mit z Gold usw., kurz mit andern Waren in den verschiedensten Proportionen. Mannigfache Tauschwerte also hat der Weizen statt eines einzigen. Aber da x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold usw. der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen y Stiefelwichse, y Seide, z Gold usw. durch einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Es folgt daher erstens: Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber: Der Tauschwert kann überhaupt nur die Ausdrucksweise, die “Erscheinungsform” eines von ihm unterscheidbaren Gehalts sein.
ある一つの商品、たとえば1クォーターの小麦は、xの靴墨や、yの絹や、zの金、などなど、要するに、自分以外の諸商品と、それぞれに異なった比率で交換される。このように、小麦は多様な(Mannigfach)交換価値を持つのであって、ただ一つの固有のそれを持つのではない。そしてxの靴墨も、yの絹も、zの金などなどは、みな1クォーターの小麦の交換価値なのだから、xの靴墨も、yの絹も、zの金などなどは、互いに置き換えることができる、もしくは互いに等しい大きさの交換価値でなけれならない。従って次のことが言える。第一に、同一の(derselben)商品の有効な交換価値たちは、一つの等しいもの(ein Gleiches)を表している。しかし第二に、およそ交換価値は、ただ、それとは区別される或る内実(Gehalt)の表現形式、「現象形態」でしかありえない。

〈1-9〉
Nehmen wir ferner zwei Waren, z.B. Weizen und Eisen. Welches immer ihr Austauschverhältnis, es ist stets darstellbar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Weizen irgendeinem Quantum Eisen gleichgesetzt wird, z.B. 1 Quarter Weizen = a Ztr. Eisen. Was besagt diese Gleichung? daß ein Gemeinsames von derselben Größe in zwei verschiednen Dingen existiert, in 1 Quarter Weizen und ebenfalls in a Ztr. Eisen. Beide sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tauschwert, muß also auf dies Dritte reduzierbar sein.
次は二つの商品を考えよう。例えば小麦と鉄だ。両者の交換の関係がどのようになっているとしても、それは常に一つの等式で表すことができる。つまり所与の小麦の数量値(Quantum)に対して、どれだけの数量値(Quantum)の鉄が等置されるかの式で表すことができる。たとえば「1クォーターの小麦=aツェントナーの鉄」である。この等式(「1クォーターの小麦=aツェントナーの鉄」)は何を語っているのだろうか? それは、大いさを一にする(derselben)、ある「共通なもの」(ein Gemeinsames)が、二つの違った物体のうちに存在しているということである。1 クォーターの小麦の内に、そして同じくaツェントナーの鉄の内に。小麦と鉄の両者はしたがって「ある一つの第三のもの」と等しい。この第三のもの自体は「あるもの」ではないし「別のもの」でもない。交換価値である限り、それはこうした第三のものに還元されうるのでなければならないのである。
〈1-10〉
Ein einfaches geometrisches Beispiel veranschauliche dies. Um den Flächeninhalt aller gradlinigen Figuren zu bestimmen und zu vergleichen, löst man sie in Dreiecke auf. Das Dreieck selbst reduziert man auf einen von seiner sichtbaren Figur ganz verschiednen Ausdruck – das halbe Produkt seiner Grundlinie mit seiner Höhe. Ebenso sind die Tauschwerte der Waren zu reduzieren auf ein Gemeinsames, wovon sie ein Mehr oder Minder darstellen.
このことは簡単な幾何学の実例で考えると明瞭になる。多数の直線で囲まれている図形の面積を計算し比較するために、それはいくつもの三角形に分割される。三角形は、その目に見える形とはまったく異なる表現─その底辺と高さの積の2分の1─に還元される。同じように、商品たちの交換価値も、その多寡を表すある「共通なもの」(Gemeinsames)に還元されるのである。
〈1-11〉
Dies Gemeinsame kann nicht eine geometrische, physikalische, chemische oder sonstige natürliche Eigenschaft der Waren sein. Ihre körperlichen Eigenschaften kommen überhaupt nur in Betracht, soweit selbe sie nutzbar machen, also zu Gebrauchswerten. Andererseits aber ist es grade die Abstraktion von ihren Gebrauchswerten, was das Austauschverhältnis <52> der Waren augenscheinlich charakterisiert. Innerhalb desselben gilt ein Gebrauchswert grade so viel wie jeder andre, wenn er nur in gehöriger Proportion vorhanden ist. Oder, wie der alte Barbon sagt:
“Die eine Warensorte ist so gut wie die andre, wenn ihr Tauschwert gleich groß ist. Da existiert keine Verschiedenheit oder Unterscheidbarkeit zwischen Dingen von gleich großem Tauschwert.”(8)
Als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedner Qualität, als Tauschwerte können sie nur verschiedner Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert.
(8) “One sort of wares are as good as another, if the value be equal. There is no difference or distinction in things of equal value … One hundred pounds worth of lead or iron, is of as great a value as one hundred pounds worth of silver and gold.” <” … Blei oder Eisen im Werte von einhundert Pfund Sterling haben gleich großen Tauschwert wie Silber und Gold im Werte von einhundert Pfund Sterling.”> (N. Barbon, l.c.p. 53 u. 7.)
この「共通なもの」(Gemeinsame)は、幾何学的また物理学的また化学的などの自然の性質ではありえない。その体的な諸性質が考慮されるのは、その諸性質そのもの(selbe)がそれを有用にしている限りにおいて、つまりそれを使用価値にしている限りにおいてである。他方、諸商品の使用価値を捨象するということこそが、まさに諸商品の交換関係の明白な性格である。この関係の(desselben)中において、ある一つの使用価値は、ふさわしい割合でそれ自身の内部に存在すれば、他の商品とちょうど同じだけと認められるのである。かの老バーボンは言っている、
「一方の商品種類は、その交換価値が同じ大きさならば、他方の商品種類と同じである。同じ大きさの交換価値をもつ諸物のあいだには差異や区別はないのである。」(八)
使用価値としては、諸商品は、なによりもまず、いろいろに違った質であるが、交換価値としては、諸商品はただいろいろに違った量でしかありえない。したがって一原子の使用価値すら含んではいないのである。
*(八)“One sort of wares are as good as another, if the value be equal. There is no difference or distinction in things of equal value … One hundred pounds worth of lead or iron, is of as great a value as one hundred pounds worth of silver and gold.” ” …価値100ポンドの鉛や鉄は、価値100ポンドの銀や金と同じ大いさの交換価値を持つ。”(N. Barbon, l.c.p. 53 u. 7.)
〈1-12〉
Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Jedoch ist uns auch das Arbeitsprodukt bereits in der Hand verwandelt. Abstrahieren wir von seinem Gebrauchswert, so abstrahieren wir auch von den körperlichen Bestandteilen und Formen, die es zum Gebrauchswert machen. Es ist nicht länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich Ding. Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgelöscht. Es ist auch nicht länger das Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder der Spinnarbeit oder sonst einer bestimmten produktiven Arbeit. Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützlicher Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.
今、その商品体から使用価値を捨象して観察すれば、そこに残るのは、それが労働の生産物であるという性質だけである。とは言え、この労働生産物も、われわれの手の内ですでに変えられている。労働生産物の使用価値を捨象するならば、それを使用価値にしている物体的な諸成分や諸形態をも捨象することになるのだ。その商品は、もはや机や家や糸やその他の有用な物体ではない。労働生産物の感覚的性状はすべて消し去られている。それはまた、指物労働や建築労働や紡績労働やその他の特定の生産的労働の生産物でも最早ない。労働生産物の有用性と共に労働生産物に表わされている労働の有用性は消え去り、したがってまたこれらの労働のいろいろな具体的形態も消え去り、これらの労働はもはや互いに区別されることなく、すべてことごとく、相等しい(gleiche)人間の労働に、抽象人間労働に、還元されているのである。
〈1-13〉
Betrachten wir nun das Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übriggeblieben als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, d.h. der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte – Warenwerte.
では、これらの労働生産物の残滓を検討しよう。それらに残っているものは、まぼろしのような、持続する(dieselbe)対象性(Gegenständlichkeit)だけであり、無差別な人間労働の、すなわちその支出の形態にはかかわりのない人間労働力の支出のただの凝固物のほかにはなにもない。この物体が表わしているのは、ただ、その生産に人間労働力が支出され、人間労働が積み上げられたということだけだ。こうした、これらに共通の社会的(gemeinschaftlichen)実体の結晶として、それは価値─商品価値なのである。
〈1-14〉
<53> Im Austauschverhältnis der Waren selbst erschien uns ihr Tauschwert als etwas von ihren Gebrauchswerten durchaus Unabhängiges. Abstrahiert man nun wirklich vom Gebrauchswert der Arbeitsprodukte, so erhält man ihren Wert, wie er eben bestimmt ward. Das Gemeinsame, was sich im Austauschverhältnis oder Tauschwert der Ware darstellt, ist also ihr Wert. Der Fortgang der Untersuchung wird uns zurückführen zum Tauschwert als der notwendigen Ausdrucksweise oder Erscheinungsform des Werts, welcher zunächst jedoch unabhängig von dieser Form zu betrachten ist.
上記の交換関係において、諸商品の交換価値は、使用価値とはまったくかかわりのない何かとしてわれわれの前に現れた。そこで労働生産物から使用価値を捨象してみたところ、その結果、いま上に規定したように、その価値が得られた。ゆえに、諸商品の交換関係および諸商品の交換価値のうちに表されている「共通のもの」は、商品の価値である。この研究がもう少し進んだあと、われわれは、価値の必然的な表現形式または現象形態としての交換価値に連れ戻されるであろう。しかしこの価値は、さしあたりはまずそうした形態にはかかわりなしに考察されなければならない。
〈1-15〉
Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist. Wie nun die Größe seines Werts messen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen “wertbildenden Substanz”, der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst mißt sich an ihrer Zeitdauer, und die Arbeitszeit besitzt wieder ihren Maßstab an bestimmten Zeitteilen, wie Stunde, Tag usw.
このように、ある一つの使用価値または財の価値はただ一つの値を持つ。それはそこに抽象的な人間労働が対象化され、物質化されているからである。では、その価値の大いさ(Größe)はどのように測られるのだろうか。それは、それらの中に含まれる「価値形成の実体」である労働の、その数量値(Quantum)を通じてである。労働の量(Quantität)は、その経過時間で比較されるが、労働時間もまた、一時間、一日など、ある特定の幅の度量標準を持っている。
〈1-16〉
Es könnte scheinen, daß, wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Die gesamte Arbeitskraft der Gesellschaft, die sich in den Werten der Warenwelt darstellt, gilt hier als eine und dieselbe menschliche Arbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen Arbeitskräften besteht. Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit sie den Charakter einer gesellschaftlichen Durchschnitts-Arbeitskraft besitzt und als solche gesellschaftliche Durchschnitts-Arbeitskraft wirkt, also in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt, um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen. Nach der Einführung des Dampfwebstuhls in England z.B. genügte vielleicht halb so viel Arbeit als vorher, um ein gegebenes Quantum Garn in Gewebe zu verwandeln. Der englische Handweber brauchte zu dieser Verwandlung in der Tat nach wie vor dieselbe Arbeitszeit, aber das Produkt seiner individuellen Arbeitsstunde stellte jetzt nur noch eine halbe gesellschaftliche Arbeitsstunde dar und fiel daher auf die Hälfte seines frühern Werts.
次のように思われるかもしれない。ある商品の価値が、その生産に費やされる労働の数量値(Arbeitsquantum)によって決まるのであれば、怠け者や不器用な人など、その商品の製造にはより多くの時間が必要となるので、その商品の価値はより高くなるのでは、と。ところが、この労働、価値の実体を構成する労働は、相等しい(gleiche)人間の労働であり、人間労働力の一定の(dieselbe)支出なのである。社会の労働力全体、商品世界の価値に表現されるそれは、ひとかたまりで(eine)なおかつ(und)一定出力の(dieselbe)人間労働力なのである。それは無数の個別労働力で構成されているのであるが。その個々の労働力は、他と同じの、同一出力の人間労働力である。これ(個々の労働力)は社会の平均的な労働力という性格をもち、社会的平均労働力として機能するのだから、ある一つの商品の生産に必要ということになるのは、平均として求められる、社会的に求められる労働時間だけなのだ。社会的に求められる労働時間であるが、これは、何らかの使用価値を、現存する社会的に正常な生産条件と、社会的に平均的な熟練度と強度でもって表す(darstellen)ところの労働時間である。たとえば、イギリスで蒸気織機が導入された後、ある特定の数量値(Quantum)の糸を織物に変えるのに必要な労働時間は、それ以前の約半分になった。イギリスの織工たちは、糸を織物に加工するために以前と同じ(dieselbe)労働時間を要したが、彼の一時間あたりの労働の生産物は、今や社会的労働時間の半分を表す(darstellen)に過ぎず、したがって、価値は以前の半分である。
〈1-17〉
<54> Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit oder die zur Herstellung eines Gebrauchswerts gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, welche seine Wertgröße bestimmt (9). Die einzelne Ware gilt hier überhaupt als Durchschnittsexemplar ihrer Art (10). Waren, worin gleich große Arbeitsquanta enthalten sind oder die in derselben Arbeitszeit hergestellt werden können, haben daher dieselbe Wertgröße. Der Wert einer Ware verhält sich zum Wert jeder andren Ware wie die zur Produktion der einen notwendige Arbeitszeit zu der für die Produktion der andren notwendigen Arbeitszeit. “Als Werte sind alle Waren nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit.”(11)
(9) Note zur 2. Ausg. “The value of them (the necessaries of life) when they are exchagend the one for another, is regulated by the quantity of labour necessarily required, and commonly taken in producing them.” “Der Wert von Gebrauchsgegenständen, sobald sie gegeneinander ausgetauscht werden, ist bestimmt durch das Quantum der zu ihrer Produktion notwendig erheischten und gewöhnlich angewandten Arbeit.” (“Some Thoughts on the Interest of Money in general, and particularly in the Public funds etc.”, London, p. 36, 37.) Diese merkwürdige anonyme Schrift des vorigen Jahrhunderts trägt kein Datum. Es geht jedoch aus ihrem Inhalt hervor, daß sie unter Georg II., etwa 1739 oder 1740, erschienen ist.
(10) “Alle Erzeugnisse der gleichen Art bilden eigentlich nur eine Masse, deren Preis allgemein und ohne Rücksicht auf die besonderen Umstände bestimmt wird.”
(11) K. Marx, l.c.p.6. <Siehe Band 13, S. 18>
仮訳
だから、社会的に求められる労働の数量値(Quantum)、もしくは、ある使用価値の生産のために社会的に求められる労働時間だけが、そのの価値の大きさ(Wertgröße)を規定している。個々の商品は、ここでは一般にその商品が属する種類の平均的なサンプルということになっているのだ。相等しい大きさの労働数量値を持つ商品同士、つまり、同じ労働時間で生産されることのできる商品同士は、したがって同じ大いさの価値をもっている。ある特定の商品の価値が他の別の商品と関係する仕方(=比率)は、当該の商品の生産に必要な労働時間が、他の別の商品の生産のために求められる労働時間と関係する仕方(=比率)と同じである。「価値としてのすべての商品は、単に凝固した労働時間の一定量であるだけだ。」(11)
〈1-18〉
Die Wertgröße einer Ware bliebe daher konstant, wäre die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit konstant. Letztere wechselt aber mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit. Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter anderen durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftliche Kombination des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsprozesses, und durch Naturverhältnisse. Dasselbe Quantum Arbeit stellt sich z.B. mit günstiger Jahreszeit in 8 Bushel Weizen dar, mit ungünstiger in nur 4. Dasselbe Quantum Arbeit liefert mehr Metalle in reichhaltigen als in armen Minen usw. Diamanten kommen selten in der Erdrinde vor, und ihre Findung kostet daher im Durchschnitt viel Arbeitszeit. Folglich stellen sie in wenig Volumen viel Arbeit dar. Jacob bezweifelt, daß Gold jemals seinen vollen Wert bezahlt <55> hat. Noch mehr gilt dies vom Diamant. Nach Eschwege hatte 1823 die achtzigjährige Gesamtausbeute der brasilischen Diamantgruben noch nicht den Preis des 11/2jährigen Durchschnittsprodukts der brasilischen Zucker oder Kaffeepflanzungen erreicht, obgleich sie viel mehr Arbeit darstellte, also mehr Wert. Mit reichhaltigeren Gruben würde dasselbe Arbeitsquantum sich in mehr Diamanten darstellen und ihr Wert sinken. Gelingt es, mit wenig Arbeit Kohle in Diamant zu verwandeln, so kann sein Wert unter den von Ziegelsteinen fallen. Allgemein: Je größer die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto größer sein Wert. Die Wertgröße einer Ware wechselt also direkt wie das Quantum und umgekehrt wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirklichenden Arbeit. <1. Auflage folgt: Wir kennen jetzt die Substanz des Werts. Es ist die Arbeit. Wir kennen sein Größenmaß. Es ist die Arbeitszeit. Seine Form, die den Wert eben zum Tausch-Wert stempelt, bleibt zu analysieren. Vorher jedoch sind die bereits gefundenen Bestimmungen etwas näher zu entwickeln.>
〈1-19〉
Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es ist dies der Fall, wenn sein Nutzen für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Boden, natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz usw. Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein. Wer durch sein Produkt sein eignes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um Ware zu produzieren, muß er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert für andre, gesellschaftliche Gebrauchswert. {Und nicht nur für andre schlechthin. Der mittelalterlichen Bauer produzierte das Zinskorn für den Feudalherrn, das Zehntkorn für den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehnkorn wurden dadurch Ware, daß sie für andre produziert waren. Um Ware zu werden, muß das Produkt dem andern, dem es als Gebrauchswert dient, durch den Austausch übertragen werden.}(11a) Endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert.
(11a) Note zur 4. Aufl. – Ich schiebe das Eingeklammerte ein, weil durch dessen Weglassung sehr häufig das Mißverständnis entstanden, jedes Produkt, das von einem andern als dem Produzenten konsumiert wird, gelte bei Marx als Ware. – F. E.
資本論を nyun とちゃんと読むための準備編1 「実体」とは?
ご無沙汰です!
イイね!が90を超えた!
思ったよりイイね!多くてうれしいけどどうしよう…
というと?
資本論の時代の人たちやカントとかヘーゲルとか、もっと昔の人(スピノザやロック)やもっともっと昔の人(アリストテレスとか)の話をぶっこもうとすると言葉がむつかしくなってしまう。
なるほどー
先日、かるちゃんとこんな話をしたのだけどどう思う?
某月某日、「スマホ」という歴史的概念について
ヘーゲルとMMTで資本論を挟み撃ちする感じで図式化したいのだけど、わかりやすくキレイに語るためには。。。
世界をシステムとして把握するときに、何らかの基本的カテゴリーから語り始めるしかないのだけれど、それはMMTにあっては政府支出であり、マルクスでは商品、ヘーゲルなら「存在」ということになります。
はあ
こうして比べるとMMTの「政府支出」というのはちょっと異様ですね。
それに先立って、政府という存在が分析されないといけません。
システムは動くものである以上、構造(仕組み)と動かす力がある。
じゃあその力はなんだろうね?ってことになると、MMTにおいてそれは税であり、政府によるセルフプロビジョンであるという論理になっていると。
「政府が○○する」には「政府がある(存在する)」が先立つし、同じように「リンネルを交換する」には「リンネルがある(存在する」が先立つように、やっぱ最初はヘーゲルでいいんですよ(笑
なるほど
しかし「ある」とはどういうことか?というのはヘーゲルより前から考えられていたわけですね。
デカルトやカント…?
ヘーゲルの哲学史講義がその後弟子によってまとめられているのですが、あれはおもしろいですよ。
いわゆる存在に始まる形式的な体系としては、アリストテレスの形而上学、いろいろ飛ばしてヘーゲル直近のバークリーとカントを考えてみましょう。
はい
端折って言うと、バークリーは「存在とは知覚されるもののことである」とし、カントは「時空をアプリオリな認識カテゴリーと位置付けてわれわれはそれを介して事物を認識する」としたという感じですね。
ヘーゲルはこうした主観と客観という二項対立を拒否しようとしたのだと思われます。
この二つは別のものではなくて、互いに浸透しあうもの、的な。
たとえば現代の私たちは「スマホがあります」という文の意味を了解しますが、前世紀には意味がわかる人は一人もいなかったと思われます。
スマホってなんだってなります
iPhone の発売は2007年なんですね。
そのあとしばらくしても、まだ「スマホ」概念はなかったと思われます。
Androidがだいぶ普及してからですよね。
ところで、仮に今の観察者が2008年くらいを観測するとスマホの存在が確認できるはず。
この期間にスマホという概念が生成したのだけれど、これは主体(サブジェクト)と客体(オブジェクト)が相互に浸透した結果としての反射なんです。
かくして今の私たちは「それ」を知覚すると(見たりすると)その反射として「スマホがあるな」という概念が返ってくる。
なるほど
なんとなく意味わかりましたでしょうか?
これは、われわれがスマホ概念がある時代となかった時代の両方を知っているから語れる話なんですね。
そんな風に、昔の人が言わんとしていることを我々が理解しようとするときに、現代の知識を使うとわかりやすくなる局面は多々あるでしょう。
「ジョブズは前世紀からスマホを構想していた!」というように。
なんとなく分かりました
これから資本論を読み込んでいく作業でも、この手を使わわない理由はありません。
あとこれ自分で気づいていなかったのだけど、ぼくが語るMMTや資本論は「ポストモダン的だ」と批評されたことがあって、確かにそういうところはあるのでしょう。
そこで開き直って、その後の思想もじゃんじゃん援用していくつもりです。
何しろ、ポストモダン的社会批評はマルクス抜きに語れないと思います。さらに、マルクス主義から距離を置く反マルクス主義思想すらも、まさにそのことによってマルクスを踏まえているわけですね。
というわけで、最初に語っておきたいのがソシュールの言語学というか、丸山圭一郎によるその説明です。

「〈犬〉という語は、〈狼〉なる語が存在しない限り、狼をも指すであろう。このように語は体系に依存している。孤立した記号というものはないのである。」(『ソシュールの思想』96頁)
「それぞれ「犬」と「狼」という語で指し示される動物が、はじめから二種類に概念別されねばならぬという必然性はどこにもないのと同様に、あらゆる知覚や経験、そして森羅万象は、言語の網を通して見る以前は連続体である。(中略)また、我々にとって、太陽光線のスペクトルや虹の色が、紫、藍、青、緑、黄、橙、赤の七色から構成されているという事実ほど、客観的で普遍的な物理的現実に基づいたものはないように思われる。ところが、英語ではこの同じスペクトルを、purple、blue、green、yellow、orange、redの六色に区切るし、ローデシアの一言語であるショナ語では三色、ウバンギの一言語であるサンゴ語では二色、リベリアの一言語であるバッサ語でも、二色にしか区切らないという事実は何を物語っているのであろうか。言語はまさに、それが話されている社会にのみ共通な、経験の固有な概念化・構造化であって、各言語は一つの世界像であり、それを通して連続の現実を非連続化するプリズムであり、独自のゲシュタルトなのである。」(『ソシュールの思想』118~119頁)
次に、フッサールの『現象学の理念』から
「赤の個別的直観を一度ないし数度おこない、純粋に内在的なものを固持し、現象学的還元にとりかかるものとする。わたしは、赤がふつうに意味するところのもの、超越的に統合されて、たとえば、わたしの机のうえの吸取紙の赤、等々としてあらわれるのをきりすて、こうして純粋に直観的に赤一般という観念の意味を、類としての赤を、たとえばあれこれの赤をはなれて直観される同一の一般者を、つくりあげる。個別性そのものはもはや思念されず、あれこれの赤ではなく、赤一般が思念される。じっさいに純粋に直観的にそうしたこころみをおこなった場合に、赤一般とはなにか、それはなにを意味するのか、その本質はなにか、といったことをなおも疑うのは筋のとおったことであろうか。われわれはたしかにそれを直観していて、赤という種類がそこにあり、そこで思念されているのだ。」(『現象学の理念』87~88頁)
ここのフッサールの「純粋赤」の論じ方は、ヘーゲルの「純粋有」「純粋無」の論じ方とそっくり。
資本論のマルクスは、これとちょうど同じように「商品」という概念から「あらゆる使用価値」を取り除いてなお「残る何か」を調べています。
さて、上の図で、「狼」は「犬」でも「山犬」でも「野犬」でもないことによって「狼」と言われます。
同じことを「色」で考えます。

ある色は、「他の色でないことによってその色」であるわけですね。
何が言いたいかというと
「言語学の父」ソシュールは1857年 – 1913年の人で、ヘーゲルやマルクスからの影響関係は語られないけれど、Subject-Objectという二項対立でなく、連関と連鎖で存在を考える思考様式はヘーゲルあたりに始まっているのです。
でも、この話がどうして存在論(オントロジー)的なのかは日本語感覚ではわかりにくい。
それはこういう感じです↓

資本論にこんな図が出てきますが、似ています。

おお~
これに先立ってアリストテレスが引用されていて
「アリストテレスは『五台の寝台=一軒の家』は『五台の寝台=これこれの額の貨幣』と『違わない』と語っている。」
?
等置する、ということは、すなわち「違いがないということにする」という意味ですね。
different ではない、つまり右辺は左辺と「indifferent である」。
インディファレント…
MMTと資本論を繋ぐ indifference
ここで思考をMMTに飛ばすとですね。
「価格は売り手と借り手のインディファレントな水準を表す」、というのはMMTの価格理論の重要な出発点なんです。
マルクスもそうだよということ。
”markets allocating by price as they express indifference levels between buyers and sellers”
これ↑はモズラーの言葉なわけだけれども、上の資本論の図の左辺、つまり「20エレのリンネル」、「1着の上着」、「10ポンドの茶」…というそれぞれは indifferent な水準で並べられいる。
だからモズラーは資本論と同じ話をしているということになる。
彼がそれに気づいていても、そうでないにしても。
indifference という言葉は、異なるモノの価値が同じになる(=差がない)ところで価格が決まるという意味で、主流経済学ではあまり出てきませんがMMTでは重要なはずなので覚えてくださいね!
はい!
というわけで「実体」の話
というわけでこんな感じだとむつかしすぎるか?
何がやりたいのかがよくわからないワンね
うん。ええとねえ。
ここは「資本論をちゃんと読む」っていうテーマでやるわけだけど、そういうテーマの本はすでにたくさんあるし、探すとサイトもぼちぼちある。
で、みんなそれなりに「ちゃんと」書こうとしているんだよね。
同じことをやっても意味ないワンね
出だしが有名なんだけど知ってるよね
なんだっけ?
「資本制生産様式が主流を占める諸社会の富は、商品の膨大な集まりとして現れる…」
うん、
そこはみんな力こぶ入れて語っているし、ぼくもそうしたい(笑
じゃあどうしよう。
序文から始めるパターンもある。けどやっぱ本文からかな。
本文の最初の節の見出しに注目!
ここが新しい(笑
節の見出し。。。

この「実体」って何でしょうね?
ご丁寧に「価値(価値実体 価値量)」とここで入れる意味は何でしょうか。
本文を読むとわかるしくみなのかな
いや、ぼくはこれ、現代のほとんどの人にはわからないと思う。
そうなの?!
たとえば宇野弘蔵という人は、「マルクスがこの節で価値の実体規定を与えているのはおかしい!」みたいな読み方をして、資本論の論理構成を独自のものに組み替えるんだよ。
そうなんだ
前にヘッドホンが教えてくれたのを引用するね。
マルクスは,価値形態論においても,したがってまた価値尺度論においても,商品はその価値を,その生産に社会的に必要とされる労働によって規定され,価値形態はそれをそのままに表示するものとして解明されなければならないとしている。貨幣の価値尺度としての機能も,価格の価値との不一致の可能性を認めながらも,価値通りに表示するものとして尺度するものと考えているのである。しかし商品経済は,マルクス自身も十分によく知っているように,価格の変動を通して価値法則を貫徹せしめるのであって,商品の価値形態も,貨幣の価値尺度機能も,かかる価格の価値を中心とした変動を容れる形態であり,機能である。それは最初から商品の価値を価値通りに表示するものとしたのでは,むしろそういう特殊の性格が見失われることになる。価値の実体論的規定を形態規定に先だって与えたことは,形態論の方法を誤ることにならざるをえなかったといってよい。
(宇野弘蔵『宇野弘蔵著作集 第九巻』岩波書店,211ページ)
一般に形態は実体あっての形態であって,先ず実体が明らかにされなければ,形態は展開されないーと考えられるであるが,しかし商品論にあっては,したがってまた資本家的商品経済を支配する経済法則を明らかにする経済学の原理論にあっては,それはむしろいわゆる本末転倒といってよい。商品経済がその商品価値の実体となすものは,単に商品経済にのみ特有なものに基くのではない。労働価値論によって価値の実体をなすものとして明らかにされる,商品の生産に社会的に必要とされる労働は,社会的に必要とされる生産物が商品形態を与えられないでも,社会的実体をなすものである。しかしまたかかる社会的実体は,それ自身として商品価値の実体をなすものとしてその形態を展開するわけではない。むしろ逆である。商品形態は,共同体と共同体との間に発生して,共同体の内部に滲透していって,それらの共同体を一社会に結合しつつ社会的実体を把握することになるのであって,形態自身はいわば外から実体を包摂し,収容するのである。もちろん形態自身にも社会的実体を包摂しうる等置関係の形式が有るのであるが,しかしそれはすでに繰り返し述べてきたように,実体をそのままに等置関係におくものではなく,貨幣を通して間接的に,しかも繰り返し行われる売買関係の内に,社会的実体を包摂する形態となるのである。それは実体をそのままに包摂する,実体あっての形態としては,決してその特殊の性質を明らかにしえないものなのである。
(宇野弘蔵『宇野弘蔵著作集 第九巻』岩波書店,212-213ページ)
『資本論』は,第一巻の第一章商品の最初に,生産物の商品形態が主題たることを指摘し,使用価値と価値とが商品の二要因をなすことを明らかにすると直ちに価値の実体を,商品の生産によってその生産に要する労働として説くのであるが,商品の生産過程自身はここではなお解明されてはいない。また実際商品は資本と異なって生産の形態をなすものではなく,その生産過程なるものは,一般的なる生産過程を包摂する特殊形態の生産過程として説きうるものではない。マルクスは,本文に指摘したように,後に「絶対的剰余価値の生産」と題する第三篇において資本の生産過程を説くとき始めて,その篇の最初に「労働過程」を説くのである。しかしすでに第一章で商品の生産を説いているために,反ってこの「労働過程」は一般的な労働生産過程としての規定を十分には展開しえないことになっている。
(宇野弘蔵『経済原論』岩波文庫,25-26ページ)
ぼくは宇野のことをよく知らなかったのだけど、とてもユニークな人だなとは思っていて、でも、動機がよくわからなかったんです。
でも宇野がああいう独自のことができしまったのかというと、ドイツ語の Substanz という言葉の意味を完全につかみそこなったせいだなと今は思うんだよね。
ヘーゲルが使った Substanz という言葉の意味ね。
その言葉は大事なわけワンね
うん。
とくに宇野が言うような、「一般に形態は実体あっての形態であって,先ず実体が明らかにされなければ,形態は展開されないーと考えられる」ということはまったくないのよ。
観察者が「明らか」にしていようがしていなかろうが、サブスタンツは形態を変えるんです。つぼみが花になり実になるように。
そういう意味ならそうワンね
うん。
資本論の論理展開は、ヘーゲルのそれが下敷きになっているのだけど、
「価値(価値実体と価値量)」、Wert(Wertsubstanz, Wertgröße) という見出しは、この時点でそれを宣言しているようなものなんだよ。
ヘーゲルを知っている人なら一目で気づくの。
ヘーゲルのエンチクロペディー(Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse、哲学的知識体系の百科事典・要綱)という壮大な著作があるのだけど、それが下敷きなんですよ。
はー
というわけで、「価値(価値実体 価値量)」について語りたいのだけど、我々としてはそのまえに、例えばドイツ語の Substanz と日本語の「実体」という言葉には意味内容に違いが出てしまうだよね、という話を挟むことにしなければ。。。
続・資本論を「ちゃんと」読むにあたり
前回(資本論を「ちゃんと」読むにあたり)のつづき

もう一つマルクス 資本論の哲学 (岩波新書) | 熊野 純彦 から

一枚目の図、こういう図を見てみたかった!商品が持ち主を変える図!生産から流通、消費に移る、分かりやすい!
この図にないのは財政支出と税、ということになりますね。
貨幣の生産と消費?
次元を増やす感じ?垂直方向に貨幣の生産と消費の軸が追加されるイメージですかね。
サーキットセオリーという考え方がそれです
サーキットセオリー(^^)初めて聞く言葉です。
MMTの手法として紹介されてました

新たな財政再建不要論:現代貨幣理論(MMT)
このセンセイの文はネタに使えるかも。
【MMTの貨幣論】
このように考えるのは、彼らが、主流派経済学が想定してきたものとは異なる貨幣論に立脚していることが大きく影響しています。主流派経済学は、貨幣の起源を物々交換が直面する「二重の欲望」という困難性を克服するために登場した「一般的受容性」に求めます。これは金属主義(Metallism)と呼ばれている立場です。これに対して、MMTは、貨幣の起源を、政府が発行し、それによって納税することを要求することに求めています。これは表券主義(Chartalism)と呼ばれている考え方です。このため、MMTは、しばしば新表券主義(Neo-Chartalism)とも呼ばれています。
この引用箇所、どう思いますか?
二重の欲望、とか一般的受容性とか小難しい言葉が満載で一読して意味が分かりません。
表券主義ということばは聞いたことがあります、nyunさんのブログで
一般的受容性ってもしかして、皆が価値があると思っているから貨幣は流通するという考えかなぁ。
ダメだなあと思うの「これに対して」というレトリックなんです。
金属主義というのと表券主義が対立するように扱っているからですか?
このバカが言う「一般受容性」というやつがあるものを政府が発行して納税させているという考えは、どちらに入りますかね?
両方?
そうなりますよね
なるほど
「一つに過ぎないものを分けて考えてしまう。」
スピノザ?!
まあこれはとてもよくあるバカな論法なのですが、「MMTは表券主義である」というようにそれ自体は間違いとは言い切れない小さな真実をあげつらうことによって、それとは「金属主義」なるものの「一般的受容性」を軽視しているかのようなウソをいうわけです。
マルクスだって、むしろ「信用貨幣」をちゃんと論じたほとんど最初の人の一人であるにもかかわらず「金属主義」の仲間に入れられてしまうとか。
ほんとうに学者ってバカしかいないのかな?と思ってしまうわけです。
資本論で言えば、金なり銀なりの硬貨が紙幣になり、それは記号なのだということがちゃんと書いてありますよね。その同じ考えは現代の電子マネーにも展開できるわけですよ。
そのように考えるためのとりかかりとして、熊野さんのこの図を発展させていけばいい

流通の媒介者としての姿では、金は、ありとあらゆる侮辱をこうむり、けずりとられ、そしてただの象徴的な紙切れになるまでうすくされさえした。だが貨幣としては、これにその金色の栄光がかえしあたえられる。それは奴僕から主人になる。それはただの下働きから諸商品の神となるのである。
「経済学批判」岩波文庫 p160
諸商品の交換価値がその交換過程をつうじて金貨に結晶するように、金貨は通流のなかで自分自身の象徴に昇華し、まず摩滅した金鋳貨の形態をとり、つぎには補助金属鋳貨の形態をとり、そしてついには無価値な徴票の、紙券の、つまり単なる価値表章の形態をとるのである。
同 p147
そうですね。
そして、資本論の交換過程の記述は、熊野や佐々木のような「図」を思わず書きたくなるんです。
図を描きたくなると言うとMMTもそうで、こんなのを描いていたことを懐かしく思い出します。

懐かしい(^^)これで勉強しました!
ん?
どこが似ているかと言うと、経済をインプットとアウトプットがあるシステムとして、まるっと把握しようとするホーリスティックなビューなんですね。
系、つまりシステム思考なんです。
生態系もまた「系」ですから。熊野さんの図を見て、資本論の前半を読み直してますますそう思えてきました。
そして、貨幣や商品を「記号」と見る考え方。これも新しい。
昨今流行りのグラフ理論を先取りしている感じがします。
対して経済学の考え方は、結局のところ、こうなんです。

あるいはせいぜい、こう

ここには法則がない
経済学者は、だから好きなことが言える
それぞれの「記号」が独立しているものとして解釈していいなら、解釈は無限に作れてしまいます。
なるほど
なのだけど、マルクスが新しいのはこういう感じで

システムに入ったWは必ず等価なGとつながっているとか、システムから出ていくWの前には必ず等価なGがある、みたいな。
あと。。。
「誰かの売りは誰かの買いである」
「システムを循環する金貨の量は、出入りがない限り不変」
こうした絶対事実から論理的な推論を組み立てていくのは、まさにグラフ理論的なんですよね。
なるほど〜

MMTは「民間(非政府部門)の純金融資産は、政府の累積財政赤字である」という絶対事実を出発点の一つとしますけれど、考え方が全く同じなんですよ。
現代のわれわれは、すでに整理されている「グラフ理論」などを知っているのでマルクスの文を「なるほどそういう感じか!」と理解することができるわけですが、先端を行き過ぎていると、読者が付いていけない。
マルクス自身、表現に苦心したはずなんです。
だからわれわれはマルクスを読むときは、「いつもシステムで考えている人なんだ」という意識を手放さないことが肝要だと思います。これはMMTも同じですね。
それは石倉先生が言われる「オリジナルの議論を、どこまで「一貫したもの」と把握できるのかを考え抜く態度」と同じものだと思います。
だからマルクスの言いたかったことを視覚化していくという作業が重要になるのですね
そういうことになりますね
視覚というか、幾何的な把握?
ここは本当にスピノザと通じるところがあります。
スピノザと幾何的な把握はどのように通じますか?
そもそもエチカはユークリッドの「原論」の形式で書かれているわけで。。。
それはおいおいやりましょう(笑)
かるちゃんはフーリエ変換習いました?
習ってないです
ではNMR分析は?
分子構造を解析する核磁気共鳴
学生時代にやった気がします
なんかスペクトルを解読する

それです!
たとえば純粋なエタノールだと、こういうスペクトルが観察される

今となってはなんでこうなるのか思い出せない…でも勉強した記憶はあります
このスペクトルは、もとの測定データをフーリエ変換して見やすくしたやつなんですね。変換する前のFID信号を見ても人間には何が何だかわからない。

へぇ〜
これは、同じものの「見方」を変えているだけなんです。
こういうイメージ

おおー
「時間領域を周波数領域に変換する」というのはこういうことなんですね
これがフーリエ変換!
これはフーリエ変換の一つの実用例、というわけです。
変換の本質は、あらゆる曲線は正弦波の重ね合わせで表現できる!ということでしょうね。

昔NHKのテレビでこういうのやってて見た記憶が。
上のNMRは典型的だと思いますけれど、マルクスにも見られるのは「視点」をガラリと変えて、もういちど全体を把握し直すという思考ですね。
なるほど
そうすると、「一見したところ○○」なものがぜんぜん別の相貌で「現れる」。
現代で言うと、国債は「一見したところ」財源のためということになっている。
しかし!
こうやって「見る」と、国債のグロテスクな談合構造がありありと見えるわけです。
NMRはまさにそうなのですが、見方を変えて、見やすくしてからさらに細かく「見る」のですね。
たとえば、この黄色く囲ったあたりを特に「よく見る」とか
そうですね
それが科学ですよね!
ですね(^o^)
だから「主流経済学は○○観でありマルクスなりMMTは××観である」みたいな主張は、バカな非科学的妄想にしか見えないんですよ。
わざわざ一番わかりにくいビューのままで、それぞれが勝手に好きな物語をでっちあげる。
それがまっとうな議論と言えますか?
わんわんわんわんわわんわんわ
ニュんさんのスイッチが(^o^)
マルクスのデビュー作「哲学の貧困」もそうですが、「資本論」でも「経済学は自分でわざわざそのように観察したものを、自分が発見したかのように説明する」というような批判をしていて、そんな箇所に出会うと楽しくなりますね。

GとWの話に戻ると、Wの移動を「持ち主が変わった」と把握しますよね。これはとても現代的だと思います。
この図、持ち主を書いたらもっと分かりやすいのになと思ったり

わたくしもちょっと描いてみましょう

マルクスって、こういう「状態変化」的な把握をしてますよね。
ふむふむ
現代のわれわれはこういう思考に慣れているので、次のこの図にもついていけると思います。
どうですか?

Aさんが商品Wを所有していて、Bさんに4千で売った?
これはグラフ理論的な表記です。
紙幣は「記号」であり、それは当然「誰かが持っているものである」と気づいていたマルクスは、ほとんどこの理解に到達していたわけです。だから、最初からそう考えて読むべきだと思うんでよね。
「オリジナルの議論を、どこまで「一貫したもの」と把握できるのかを考え抜く」
(石倉雅男先生)
なるほど
というわけで思考を進めましょう。わたくしたちの理解では、IOUも商品でしたよね。
だからこれも理解できる

AさんがIOUを発行して、Bさんから4000受け取った
ん-
そうではなくてこのIOUは「債務証書」のつもりです。
上のAさんは「誰かの債務証書」を持っていて、それをBさんに4000で売ったことの描写です。
なるほど
資本論の交換過程のところで、リンネル織布者さんは、まず手持ちのリンネルを市場に持ち込んで2ポンド金貨を手に入れます。

はい
こうも書けます

ふむふむ
次に、その金貨で別の人から聖書を買います。
こうでしょうか

リンネル織布者さんが聖書を買いました
これからここでは、資本論をこんな感覚で読んでみようと思うんです。
マルの中の下の数字はその人の「正味のお金」ですが、マルクスが単に「お金」と言ったときに、それはこの「正味のお金」なのか、それとも「金貨」なのかをちゃんと区別するわけです。
商品としての金貨と、計算貨幣としての金貨みたいな感じですかね
好みとしては「計算貨幣」でなく「計算単位」かなあ。
とにかく図の通り(笑)
そう理解します
なるほど(^^)
図の実物側(上)と数字側(下)というか。
ふむふむ、理解できます
現代なら一般化して「(文字、数字)と表記する」とか言いそう
コンピュータのプログラミングとかでも
面白い(^^♪
ほんとに\(^o^)/
熊野さんの図は間違いじゃないけれど、つまらない
こちらはそれでいてちゃんと「系の中の金貨の量は不変」とか「数字の合計は不変」という真理を維持しているでしょう?
たしかに!
わたくしは最近、流体粒子のシミュレーションなんかもやるのですが、ほんと同じだなって思うんですよね。
粒子の性質をいくつかのパラメーターとして定義して、数字をぶち込んで、ランダムに衝突させたりするとか。
そんな、現代の工学の先端に近いところと同じ思考をマルクスはしてるぞ!としか思えない。
マルクスって天才なんだなぁ
シミュレーションで、粒子が動く「場」を考えなくてはいけないんですね。
重力場とか電場とか磁場とか。
マルクス理論では、それが mode of production 、生産様式にあたるという感じです。
なるほど
シミュレーションすると「国債をどんどん発行しましょう!」という立場をとる粒子のとこにはどんどん「数字」が集まる、みたいな。
多くの粒子は死ぬんですけどね。
(イメージです)
ひえ~( ゚Д゚)
(たぶん死ぬ粒子の側)
歴史的には矛盾に気づく粒子たちが団結して革命になるはず?
そうでないと、子供がかわいそすぎる( ;∀;)
結論からいうと「場の条件」として「生産手段の私有」を維持する限り、どうしても格差は拡大するんです。
ふむふむ
プルードン氏の言うようになるはずがない。それは法則に反しているわけで逆に悪いことが起こるか、せいぜい破滅の速度を落とすくらいで。
たとえ消費税が廃止になってもあんまり意味ないんです。
問題は生産様式、生産手段の私有にあると
というよりも、それが支配的な条件であることに多くの人が気づいていないことかなと。
たしかに、今の状態が当たり前すぎて、悪いことだと気づけないかも
経済学者のように変な思考をせずに科学的に考えるとJG以外にないと思われるんですよね
なんで反対する人がいるんか理解ができないんですよね
自分はなにも難しい事は分からないんですけど、さいしょ直観でJGいいと思ったんです。
具体例をだせとかオラついている人たちの気持ちが全然理解できないんです
なんで自分らの利益になること、権利の保障を恐れるのか
「異なる枠組みを前提にするMMTに対しては、これまでの財政再建否定論に対するのとは別の検討を必要とします。その理論的な起源にまで遡って、その議論を丁寧に吟味する必要があるように思います。」
だそうで
これはいったい
いまのは、上の 齋藤潤 センセイの締めの言葉ですが学者はこうなっちゃうわけですよ
「丁寧」だ????
わんわんわんわんんわんわんわんわん
わーにゅんさん落ち着いて~(^^)
資本論に戻りまかすか(笑
フーリエ変換ってMMTと似てるワンね。
「数字のほうのお金」は、預金とか現金とか、さまざまな IOU の重ね合わせである、とか。
確かに
本文を読み始める前にあと一回、今日説明した考え方でマルクスの「交換」を分析してみようと思いまーす
資本論を「ちゃんと」読むにあたり
「オリジナルの議論」を、どこまで「一貫したもの」と把握できるのかを考え抜くという作業は、やはり欠かせないのではないか、と今になって痛感しています
研究室訪問 経済学研究科教授 石倉雅男
以下の引用は、昨年、つまり2020年の8月に急逝された一橋大学大学院経済学研究科の石倉雅男教授が、わたくしの若い友人であり、先生の最後の弟子のひとりであるヘッドホン氏宛ての、亡くなる二か月ほど前の 2020年6月28日 に送られたメールの内容になります。公開に当たってはヘッドホン氏の許可をいただきました。
鈴木様
ご連絡御礼.
おそらく,MMTの著者たちは,マルクスは「商品貨幣論」であると理解していると思います.また,マルクス経済学を講じている多くの先生方も,『資本論』第1部で「一般的等価物」の機能が「gold」に固定化した場合について論じられているので,「gold」が本来の貨幣であるというのがマルクス自身の見解であると判断しておられると思います.
しかし,マルクス経済学の立場をとるとしても,『資本論』第1部の論理段階に留まらないで,より具体的な次元で貨幣や金融の仕組みを考察する場合には,中央銀行・民間銀行・非銀行民間・政府などの
政府部門が関係する「決済システム」では「銀行預金」(民間銀行の負債)が決済手段として用いられること,実物資産としての「gold」と「銀行の預金債務」は性格が異なることを,ふつうに認識している人も,少なからずいます.私もそのような立場です.蛇足ながら,私自身は,『資本論』第1部第1章の商品・貨幣論から出発する場合でも,「金属貨幣」という実物資産ではなく,銀行の預金債務が決済手段として用いられる実際の取引を考察することは,十分に可能であると考えています.(このような話は,拙著の第2版のほうにも書いてあります.)
また,(私自身はそこまで勉強できていませんが)マルクスが『資本論』第3部の利子生み資本論とか信用論で,(銀行の信用創造の仕組みを詳しく検討することまでは,マルクスは生前,出来なかったようですが),「信用貨幣」を用いた決済と言ってよい商品取引と金融取引について言及している所は,たくさんあります.マルクスの草稿を研究するためには,ドイツ語の読解能力は不可欠であると思いますが,草稿研究に従事しないかぎりは,『資本論』の原文を少し確認するくらいであれば,(私の場合には,昔の一橋大学小平分校で習った)ドイツ語入門で十分です.MMTのように中央銀行と政府部門,民間銀行,非金融民間の制度部門間の資金循環を念頭におく分析視角の検討を中心に研究を進める場合には,研究時間の配分の観点から言うと,マルクスの原文を詳しく検討する時間は,無いと思います.
また,MMTのほか,ポストケインズ派経済学を吟味し,検討する場合には,商品貨幣論と信用貨幣論の違いという論点だけでは,問題の焦点に迫ることは難しいと思います.(ポストケインズ派経済学を長年研究している人々,たとえば,明治大学商学部名誉教授の渡辺良夫先生も,そのように言っておられました.)
伝統的な「マルクス経済学」の教科書(―拙著は「伝統的な立場の教科書」ではないです)に書いてある古典的な「商品貨幣論」とその機械的適用[「世界貨幣は現代でも以前として金である」という類いの認識]は,実際の金融システムを検討するさいには,まったく役に立たないと私は思います.
石倉
わたくし nyun はこの頃にヘッドホン氏と知り合い、石倉先生のお人柄やおおよその考え方を把握したうえで、おそらく近い将来にお目にかかってMMTや資本論について議論することができるだろうと予感し、その機会を楽しみにしていたものです。
その夢は実現しませんでした。
ただわたくしはその後の一年余りの思考を経て、今ようやく先生の知的好奇心を恐らくは大いなる驚きを持って満足させることができるだけの水準の答案が書けるようになっていると思っています。
一言で言えば『マルクスは「商品貨幣論」である』という問いの立て方が初めから失当だっただけなのです。「商品貨幣論」という言葉は、そうではない「別の」貨幣論なるものをあらかじめ前提にしてしまっている。
しかしマルクスにおいて「お金(Geld)」は お金(Geld) なのであって 、読者がわざわざ「商品貨幣論」と区別することはむしろその内容を台無しにしてしまう思考です。
これは、とんでもないことです。
『資本論』第1部第1章 で提示されている「お金(Geld)」の把握は、それどころか、「貨幣の本質は信用貨幣である」と言い募る人々の思考をはるかに超えた、掛け値なしの、史上最上級の知性によるものだったのであり、MMTの貨幣観を完全に先取りしています。
この事情を物理学の相対性理論になぞらえると、MMTが特殊相対性理論であるとすれば、資本論は一般相対性理論に当たると言えるでしょう
アインシュタインは光速度不変の思考実験から、特殊相対性理論を編み出し、それを一般相対性理論に「一般化」しました。(ちょうどケインズが「一般理論」において「古典派経済学」に非自発的失業を加えることで「一般化」と称したように、とも言えるでしょう)。
MMTと資本論の論理的な関係は、これとは逆に、マルクスが「一般理論」を発見し、MMTはその「特殊理論」を再発見したという形をしているのです。
ここで指摘しておきたいのは、通常の「科学(アインシュタインやケインズ)」とマルクスとMMTに見られるこの逆転現象は、マルクスやMMTの「わかりにくさ」の顕れであり、それはとりもなおさず「お金」というものの「掴みどころのなさ」にどうやら由来しているということです。
掴みどころがないのは「商品」や「仕事(労働)」も同じです。
ここで物理学の「仕事」はどうでしょうか。「力」や「座標」などが定義された後に「物体に力 F が作用し、その位置が Δx だけ変化したとき、力 F がこの物体に対してした仕事 W は W=F・Δx である」というように、 W として定義されるのが物理学における「仕事」の一例です。
対してマルクスはこうした考え方を採りません。そうではなく、私たちが「仕事」と呼んだり「交換」と 呼んだり 「商品」と呼んだりしているものはいったい何か?そうした「現実」から出発して、決して現実を離れない。
だからこそ資本論は恐ろしい。
さて、このシリーズは資本論の一文一文を丹念に読んでいくことを企図しており、さっそくそれを始めるつもりでした。
しかし 石倉先生 の文章を拝見して「 『資本論』第1部第1章の商品・貨幣論 」に相当する部分については、あらかじめ見通しを与えておいた方が良いだろうと考えを変えることになりました。
いったいマルクスは貨幣、お金というものををどのように把握していたのでしょうか?
石倉先生がおっしゃられたようにオリジナルの議論を丹念に読もうとする。そうすると一貫した美しい構造が姿を現すのです。
「お金」とは「仕事」「交換」「商品」などと呼ばれているものから浮き彫りになっていく「何か」です。
だから、そういうわけで、まずは 「仕事」「交換」「商品」は何なのかをちゃんと考え、「お金」が導出されるところまでは見通しを付けておきたく。
つづく
タイトル「Das Kapital」は「ザ★頭文字」?(その1)
「資本論」という日本語タイトルで知られている「Das Kapital」という本だけど
いきなり何?
日本語タイトルは「資本論」でいいのか?みたいに考えてしまって
「資本論」じゃなくて「資本」だとか言いたいのかな?
まあ、聞いて
ちょうど、こんなことを言っているヘンな人がいて
面白い実験が。
— 【公式】ぷろぐらみんぐ – Re:取りこぼしゼロから始める一律給付金生活 (@programingoo) November 17, 2021
人間の脳の側頭葉が状況に「疑い」あれば
落ちた財布を拾わなくさせるというもの。
やはり「財政破綻論のウソ」や
税財源脳の「労働でお金を作ってる」という
根本のウソを解除するのが先でしょうね(´・ω・`)
拾われにくい財布 | 脳トリック – YouTubehttps://t.co/aAdEHTzrU7
ただ、この動画はとても面白かったから見てほしい
道に財布が落ちていると、多くの人は気が付いて、ほどなく誰かに拾われる。
わんわん
ところがわざとこんな風に落としておくと?

なるほどワン
目立たせると、そのことによってむしろ「誰も拾わない」ということが起こるということワンね。
上の人は「労働でお金を作っている」というは「根本的なウソ」だという!
根本的なウソ?
人が賃労働をすると、お金をもらえますよね??
かるちゃんや Sarata さんが賃労働をすると、雇用主が労賃を発生させる。
かるちゃんや Sarata さんの口座のお金は、紛れもなく、そのことによって生まれている。
上の人、労働で未払給与が発生している、というのは頭にないんですね。
未払給与というIOU、お金ですね。
働でお金が生まれるっていうのはごく普通の感覚だと思います。
たぶん普通どうやってお金が生まれるの?って聞かれたら、大抵の人は働いたら生まれるって言うと思います。
なんというか、お金の生まれる源を限定しているように見えます。
かるちゃんはこんなこと言ってましたね
必ず明細まで渡されて、現実にその金額が通帳に載っても「それは嘘だ」と考えてしまう現象。
自分は二年前からこの話ばかりをしているのですが、いわゆる「エレファント・イン・ザ・ルーム」現象が起きています。
「エレファント・イン・ザ・ルーム」
会議室に巨大な象がいるのに、誰もその話題に触れない!っていうイディオムワンね
「エレファント・イン・ザ・ルーム」
会議室に巨大な象がいるのに、誰もその話題に触れない!っていうイディオムワンね
普段色々なIOUが生まれては消えているのに、彼らは統合政府IOUしか認めていない?見えてない。
うーん「銀行の信用創造!」とことさらに言う人は、思考がもっと狭いように思います。
日銀と民間銀行のIOUをことさらに見て、国債を軽く見ているでしょう?
ここ数日のtwitter 界隈でも、こういうのを見た。
おそらく、むらしん氏のこの発言に対して?
えええ?
うん。
だって、むらしんさんほど具体的なことを考えている人は珍しいくらいで、プロフィールに「ありあり」と書いている。

この、同じ事が Das Kapital と言う本にも起こっていると思います。
いちばんありありと書かれていることが「見えない」。
資本論もそうなの!?
うん
ドイツ語の Kapitalは英語の capital だけれど、英語でもわかるはず。
まずは、このサイトを見てごらん
資本金、以外に「首都」とか「大文字」とか「主要な部分」とか、いろんな意味があるワンね
頭金ていう言葉ももしかしてキャピタルから来てるんでしょうか
「頭金」の元の言葉はゲルマン語にしてもラテン語にしても、最初、とか前に、という感じの言葉ですね。
でも、頭金という言葉が出たので、これをネタにちょっと考えてみましょうか。
コドモ三名の学費を払うのに500万円が必要!
けど200万円しか払えない!、みたいな。
ふむふむ
コドモ三名の学費を払うのに500万円が必要!
けど200万円しか払えない!、みたいな。

銀行とかサラ金に500万円のIOUを発行して、すぐに200万円を頭金で支払って残りを毎月10万円で均等分割返済する場合のキャッシュフローが上ですね。
ふむふむ
ここで夫さんが、かるちゃんへの感謝として、へそくりとローンで指輪か何かを買ったとしましょうか。
えっ…絶対ないと断言できる
ま、買ったとしましょう
30万円の指輪として、20万円はすぐに支払えたけれど残り10万円が翌月払いになった

(30万は絶対ない…三千円ならある笑)
これを銀行の立場で見てみると
赤字と黒字を反転させて

あれ、にゃんちゃんも何か借金してます?
それぞれにいろんな事情があるワンね
にゃんちゃんは頭金なしのローンですね
なんかこれってクレジットカードのローンと似てる、というか一緒ですか。
そうですね、一緒です
もう一人増やしましょう

ソラタさんは頭金50万円で100万円借り入れして、毎月5万円返済のローンですね
これ銀行にとって、表の一つ一つの行のそれぞれが資産として誰かから受け取ったIOUですね。
だから銀行のバランスシート(貸借対照表)の「資産の部」に乗ります。
なるほど
私が500万のI-OUを発行して、それが銀行の資産になっている
私は500万の銀行I-OUつまり預金を受け取って、学費にあてる
あ、でも頭金200万は…
銀行に払うんだ
ん?
200万払わないと銀行は私のI-OUを500万も受け取ってくれないからか。
頭金200万は「設定」と思ってください。
ちょっと一瞬キャピタルの話題からずれるのですが、銀行にとってどのような資産なのかと言うと、こうです。

(ややこしくなるので金利はとりあえず無視)
これはわかりますか?
私が返済すると銀行にとっての資産は減る!
「現在価値」という概念が出てきたところでキャピタルの話に戻しましょう。
はい!
大事なのは、銀行は個別のIOUを、まとめて「貸出金」という資産として把握しているということです。
「貸出金」は個人に対してだけではないですよね。
はい!会社とか
団体?
じゃーん

たくさんの取引が日々動いています
ん?政府への貸付?国債のことですか。
自治体への貸付は県債、市債?
受け取ったIOUと言う意味ではそれらもここに含まれます。
なるほど
あ、銀行振込で政府支出する時って
小切手で払うから
この小切手も政府への貸付に入りますか
もちろん入ります。
そうだ、いま旬の話題の文書交通費。
あれ、政府は議員一人一人を介して政府は毎月一日に【月100万円×議員数】のIOUを発行しているというわけ。
なるほど
各議員は、各自の活動の中で、それを建て替え払いをして、領収書を受け取る。
その領収書は政府のIOUというわけ。
キャピタル(頭文字)の話に戻りますと。。。
こうした銀行の資産は日々変動するので、銀行は次の表のように「把握」するわけです。

ふむふむ
ちょっと一つ分かんなくて
領収書が政府のI-OUというのがいまいち飲み込めません
そうだそうだ!
黒柴にゃんも!
かるちゃんポイントの話
対話8 MMTやマルクス的な貨幣観(2/2)世界一よくわかるマネーのヒエラルキー

長男の資産である100は、かるちゃん発行のIOUであり、かるちゃんの負債ですね。
そうか!
長男が自分で100円のお菓子を買って、かるちゃんに領収書を持ってきたら?
それと同じなんです。
あ、わかった!飲み込めました!
私はその領収書を受け取らないといけませんものね
100万円の文書交通費という政府のIOUは、いったいいつ誰に発行されたかを考えると面白いですよ。
???
議員が調査活動にお金を使ったときかな?
もっと前だと考えることができます。
だって政府が「100万円×議員数」の負債を認識するのはいつでしょうか?
毎月一日?
そうか!
でも誰に?
この政府の負債は誰の資産だろうか?ということですね。
えー議員かな?
というか議員が支出した相手先?
国民全員と考えることができるわけです。
調査活動は国民の利益だからですか?
ですよね。
だって、そうでなければ国が支払う義理はないわけで。
そうか!
確かに〜
この件に関してわたしサメらしくなく冷静さを欠いていたから恥ずかしい…
対話大事ですね
あ、キャピタルの話に戻らなくては
この件、まさに価値の形態変化なんですよ。
??
たとえばですが、大石議員が何か印刷物を購入して有権者に配るとしましょう。
そういうことは、議員になっても、ならなくてもやっていたと思います。
そうですね
大石「未」議員が同じことをしたとき、「未」議員の仕事は国民のモノではないわけです。
大石さんの支援者のもの?
それは「解釈」の問題で、そう思う人もいるし、そうでない人もいる。
いずれにしても民間部門だけのやりとりということになる。
なるほど
そうですね
ところが大石議員の場合は同じことをしても、その領収書は政府がIOUとして受け取って、同額を支出することで決済しますよね。
このとき、領収書の価値形態が一瞬にして変わっているわけ。
領収書は最初、支出先の領収した証だったけど、政府が引き受けると決めたら政府のIOUになるという、このことについて価値形態が変わったと表現している?
(価値と言う言葉を使う前に)議員がそれを提出し、政府がそれを受け取った瞬間に「何か」が変わっていますよね。
何も提出しない場合と比較して。
印刷物という商品が、民間のモノから国民のモノに変わるワンね。
正確には、同じ一個人の活動の結果の「意味」が変わる。
政府支出が介在することによって…?
正確に言うと。。。
「その活動」が「国民のための活動」だったという認識がまず起こって、それが「政府支出」として記録される。
ちがいますか?
なんか以前お話があったカントのあれ
認識論でしたか
まず認識して始まるみたいなのありましたよね
ロックはまず物があります、から始まるけどそれは違うという(うろ覚え)
なるほどー、似てると言えるかも
ホッ
楽しい\(^o^)/
私も〜(^o^)
「先立つ政府支出」というものはどこにもなくて、政府、つまり主権者たる国民がその領収書を受け取り決済した時に「この議員のこの活動は国民のためのものであったということ」に、なる。
その現象をわれわれは「政府支出があった」と呼んでいるわけです。
なるほど!
あるいは言い方を変えて
「国民全員の資産」という漠然としたものが、決済の瞬間に「他ならないその議員のその活動」として、具体的なものとして「現れる」。
スピノザっぽい!気がする。
???
どういう感じ?(にゃんにも伝わるように)
エチカ第3部定理6証明から
「なぜなら、個物は神の属性をある一定の仕方で表現する様態である、(…)言いかえればそれは(…)神が存在し・活動する神の能力をある一定の仕方で表現する物である。」
自然の法則つまり神だけが実体で、その他の万物は神の表現する様態(モード)だという。神は私達のような人間の様態で表れたり、水として表れたり、太陽の光として表れたり。
この何か大いなるものがあり、ある条件下で、あるモードとして形を伴って表れるっていうのが似てるなって
(これは泣いてしまう)
末っ子ちゃんが雨が降っていると「神様が泣いている」って言うんです
かるちゃんはどの言葉でスピノザを想起したんだろ?
現れる、かな…
表現するっていうのと似てるから
前回のやりとり

ここで「現れる」は erscheint という語で、erscheinen という動詞です。
つながった!
資本論では、この語が Erscheinen 「出現」という名詞だったり、Erscheinungsform 、「現象形態」という形でたくさん出てくるわけです。
なるほど!
スピノザのエチカ用語だった!
もう一つ気付いたんですけどエチカに出てくる属性という言葉
「個物は神の属性をある一定の仕方で表現する様態」
一般的には実体がもつ性質を意味するそうですが、スピノザは独特の意味を込めているそうです。(100分で名著、国分功一郎さん)
人間で言えば精神に対応する「思惟」と、物体に対応する「延長」という属性を知ることができるので、一つに過ぎないものを分けて考えてしまう。

ほうほう
このところ、価値が使用価値と交換価値を二重に持っているけど、商品自体は分裂するわけじゃないっていうのと似てませんか
似てます。二通りの現れ方をしている、という感じかな。
そう!
似ているというよりも、ドイツの哲学はスピノザ解釈から出発しているところがあって、ヘーゲルもマルクスも普通にその言葉を使って議論をしているという事情ですね。
読者から見ても、こういうのを「知っている」とそういうものとして当たり前に読みとれる内容でも、「知らない」読者にはまるで分らないということになると。
それがどんなに「ありありと」書かれていたとしても、です。
そういうことだったのか!
前提となる知識がないと読み取れない
それどころか雰囲気で「こういうことだろ!」と、わかったつもりになっちゃう。
これはMMTが「インフレまで国債を発行しても大丈夫な理論だ」などと、元とはぜんぜん違う形で理解されてしまうこととそっくりなわけです。
思い出したのだけど
一番最初に岩波の資本論読んだとき、ちんぷんかんぷんだったんですよ
何が言いたいのかさっぱり分からなかった
そうだったのワンね
今見ると恥ずかしい
ひたすら恥ずかしい!
恥ずかしくないですよ。
わかろうとした人だけがだんだんわかっていくんです。
恥ずかしいってのは、こういうレベルのうちに「資本論はこうこうである」と他人に説明してしまったり、しかもそれが大学教授の立場だったりすることの方なのであって。
あと翻訳本にあほ解説を書いてしまったりわんわんわんわんわんわんわ
スイッチonしてしまった〜(^o^)
話を戻すと、「Das Kapital」は「資本論」というより「ザ★頭文字」だと思うんですよね。
イニシャルDかと思った
峠道を攻める。

よく知ってるワンね
えへへ読んだことはないけど(^o^)
Dってなんだと思いますか?
え、見当もつかないです。いま夫に聞いたらドリフトのDって。
ふふふ
それも、いち解釈ワンね
じゃーん

じつは夢、ドリームのDだったのです\(^o^)/
そうだったのかー!
「本人」がそう言っているわけでw
にゅんさん守備範囲が広すぎる!
こんな不必要な知識をほめられる日が来るとは\(^o^)/
少女マンガとかでもタイトルで伏線を張っておく、みたいのはあるじゃないですか。
それなんですよ。
なるほど
わたくしがまず思い出すのはコレ

これは「おしゃべり階段」って漫画なんですね
これもそうか

「進撃の巨人」
主人公「エレン・イェーガー」
「イェーガー」=jaeger=トウゾクカモメ=Pomarine jaeger
え、そんな意味が!
ふふふ
タイトルではなかったけど。
「頭文字D」は登場人物に説明させていましたが、「おしゃべり階段」と「進撃の巨人」は説明はない。
良く見て気づくと、なるほど。。。となるという表現です。
下のこれは「おしゃべり階段」の初回なんですが

この男の子が、左利きであることを表現されています。
ほんとだ
Das Kapital の場合は。。。

わかりますね!
アダムスミスもリカードもヘーゲルも、こういう書き方を「していない」。
あーー!!やっと分かった(遅い)
かしらもじ!
マルクスはこう書くことで表現したい「何か」があったというわけ。
それで気が付くと「ああそうか。。。」ってなる。
そういうことだったのか。なんでずっとにゅんさんが頭文字、頭文字っていってるのかやっと解りました(にぶい笑)
WーGーW
頭文字ですよ!
優れた著作というものは、二度目三度目に読む時に初めて気づくことがありますね。
そして気づいたあとは意味がまるで異なるものとして現れたり。
博覧強記の文学オタクだったマルクスはそのことをよく知っていたわけで、だからこの本は古典の引用が多用されていると。
「Das Kapita」のタイトルについてなんだけどね
Das Kapital が大きく前にあって、 Kritik der Politischen Ökonomie(政治経済学批判)という副題がついている。

1867年に出版されている。わけです。
ふんふん
そのまえに、出版を始めていたシリーズ
「Zur Kritik der Politischen Ökonomie(政治経済学批判のために)」
というのがあって、
その第一巻「Vom Kapital(資本について)」は1859年に出ている。

このシリーズはどうなったのワンか?
打ち止めになった。
資本・土地所有・賃労働・国家・外国貿易・世界市場の順序で考察する大作シリーズになる予定だったけれど、その第一部「Zur Kapital」の最初の二章までで。
「Zur Kritik der Politischen Ökonomie(政治経済学批判のために)」
その
第一巻「Vom Kapital(資本について)」
が
「Das Kapital (資本) – Kritik der politischen Ökonomie(経済学批判)」
その
第一巻「Der Produktionsprozeß des Kapitals(資本の生産過程)」
という構成に変わったということになる。
Das Kapital が前に出てきた感じワンね
うん。
先立つ 「Zur Kritik der Politischen Ökonomie(政治経済学批判のために)」 の第一巻 「Vom Kapital(資本について)」 の中で、マルクスは W-G-W、G-W-G という定式化をしているんだよね。
そしてそこで終わっている。
中断しちゃったわけだ
そう。
マルクスは W-G-W、G-W-G のところまでを書いて「構成を変える必要がある!」とか「変えた方がいい!」ということに気付いたんだと思う。
まあ「変える」ということはそうだろうね。
項目に過ぎなかった Kapital が タイトルとして前に出たときに、Vom Kapital が Das Kapital にメタモルフォーゼしている!
これはどういうことか?
ということなんだよね。
おー
放言コラム1:「資本論とMMT」その他
ドイツの経済映画“ OECONOMIA” って見たことあります? 正しいかどうかは置いといて、むっちゃ面白いっすこれ。
石塚先生のツイートから知ったんですけど
今冒頭 15分ぐらい見たんですけど、銀行がPCで貸方、借方にぱぱっと数字打ち込んで信用創造するところが映ってて、「銀行は信用創造のために別に預金がいるわけじゃないんよ」的な事をペラペラとw
んでテロップにこれ。 すごく虚業っぽさが出てる

先日ちらっとだけ見た気がしますが面白かったですか。
よかったらまたリンクをw
虚業感、というよりも、語の入れ替えの話ぽくない?これ
資本論でいえば W-G と G-W のような往復運動の表現。
リンクは以下の2件のどっちかなんですが、IPかなんかで切られてて、ドイツ国内からじゃないと視聴できないみたいなんですよ。
https://zdf.de/filme/dokumentarfilm-in-3sat/oeconomia-104.html… https://3sat.de/film/dokumentarfilmzeit/oeconomia-100.html
ほんとだ、IPアドレスで切られちゃいますね
VPN接続でないと。。。
たぶんにゅん氏的にはツッコミが足りないところがあったり、序盤で出てくる中央銀行がマネーを創造できる、ってくだりが日本だと××界隈から曲解のターゲットになったりしそうなんですが、「そもそも『利益』ってどこから来てるの?」というのを結構しつこく色んな人に聞いて回ったり、これ「正常に」日本でも流れてほしいなーと。(ドイツ語が完全にわからないんでアレなんですけど)
ただ、ドイツ語の映画だからこそ昨年の作品にも関わらず反緊縮界隈に発掘されてないのかなって思うんですよね
映画の中で、ストリートに円卓を持ち込んで5人ぐらいの有識者で話す、って演出が入るんですが、その中で結構印象的な鋭い目をしたおばちゃんがいまして、Samirah Kenawiって人だったんですが
https://falschgeldsystem.de
ここのページでは「現代の贋金は銀行によって堂々と作られている」みたいな論調で、結構過激なおばちゃんだなーって。
英語圏でもいますよね、中央銀行制度が悪いというような
映画内では悪い、までは言ってないんですけど、「なんか変じゃね?」っていう感じの演出でしたね
でも、理屈としてはおおむね正しいように思いました。
そうですね。
その人のこの動画はいい感じ
G-W-G’
新たな利潤を生むためには新たなマネーが必要で、新たなマネーが民間領域に創出されるには反対側に負債が必要、みたいな。 したがって純粋にマネーを創出できるのは中央銀行のみ、って、日本だとここだけ切り取られて○○界隈にくそみそにされそう
映画の最後の方の締めは欧州の映画っぽく環境と絡めながらこんな感じになってるんですけど、にゅんさんこのフレーズどう思います?

これはその通りだよなと
楽しむ今日は永遠にやってこない
でしょ!!
Profite というより、Kapital、資本、かな
でも今のTwitterでは絶対受け入れられないなって。
そうかなあ。。。
だとするとそれは nyun が受け入れられないということw
直訳すると今日の利益は将来の負債、今日の負債は将来の利益、じゃないですか。
資本は、過去の剰余価値が積みあがったものなわけです
これ、単純に読み取って「緊縮財政脳かw」って言われるのがオチですよね
そう思う人はゼロではないけれど
ひっくり返すとこのフレーズのままになりますね。<資本は過去の利潤が積みあがったもの
それは会計的事実ですからね
いやー・・・この辺の話が伝わるの、マイノリティだと思うなぁ本邦では・・・
MMTって言ったらほとんど財政リフレだもの・・・
自分はこのメッセージ、「資本主義のシステムは地球の環境リソースを破壊するまで止まらないよ」=>「今日の利益を追求する事は将来の負荷の前借よ」って話に受け取ったんですけどね。
持続可能ではない、って話で・・・。
地球のリソースを持ち出すのは、斉藤公平ですね
その前に、永遠にやってこない明日に備えることによって、今日の生がスポイルされるという問題の方というか。
その辺がちょっと残念なところかなとは思いました。やっぱ環境問題に引きずられちゃうんですよね。
足りないピースはMMTだな、とも思ったんですよね。
ただ、環境問題は欧州ではメディアの喧伝もあってか割と喫緊の問題としてウケるみたいなんですよねー
ガチなマルキストにとっては、今更MMT?って感じに見えると思う。
そんなのあたりまえやん、みたいな。
マルキストってJGPって解放は提示してるんでしたっけ
協働組合、アソシエーション?
確かに通貨をどうするかは弱かったですね。
レーニンが悪いんです
負のイメージが巨大すぎましたね
自由意志に基づく、出入り自由な共同体というのがとても大事ですよね。
映画は、貨幣の面からの追及にとどまってて、「価値」とか「労働」については突っ込めてなかったんですよね
そういう共同体、結構技術の発展にも寄るところがあったんじゃないかと思いますよ
それこそITをうまく使えないかなとは思いますね。
だから人工的なJGPが出てくるというイメージ
自分のイメージは、JGPは資本主義への比較的穏健なセキュリティパッチかな
この週末に作った図
じゃーん
世界初!MMTを資本論の論理的連関図

IOUは資産であり負債、って事ですね
IOUとくっついてる商品A、B、Cってどんな商品をイメージしてます?
一つ一つの IOU は Ware (商品)なわけです

一つ一つの IOU は Ware 。。。
それは上の図で言う、貨幣とか預金とか、国債とか、そういうものって事ですかね
ですです
そうすると、ここ商品A、B、Cってなるとわかりにくくないですか?(わかるひとにはわかるのかな?)
IOUは商品たりえる、、、、のかな?
なるほど、補足して書き直した方がいいですね
どっちかというと、「商品」が「商われる」にあたって認識される「価値」とIOUの表層の一部がくっ付いてるイメージかなーって・・・
表層の一部、といったのは「商い」に供されるIOUが「ありがとう」などの広義のIOUではないんじゃないかなって。
やっぱ資本論をちゃんと読むべきですよw
間違ってる?www
というか、「商品」の分析が大事だなと
あ、そこは「ちゃんと」かどうかは解らないですけど読みました。
そらんじられるほどじゃないんですけど・・・
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine “ungeheure Warensammlung”, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.
この Ware に IOUは入るんですよ
あー、「商品」に引きずられてますね自分
だってお金も富だと思っているじゃないですか、人びとは
で、次の箇所
Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache. Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d.h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel.
IOUはこの Ding なんです。英語のthing。
Waren ってか、Sachen
いや、Ding
Dinge の方がいいか
そうですね
これは重要です
カントの Ding an sich とか。
これ、Wareを「商品」と訳すの相当誤読の引力ありますよ
そう思います!
だからちゃんと読む、を始めたと言ってもいいかも
上に続く一文
Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier usw., ist unter doppelten Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität.
Spielwarenとか言いますもんね。こっちは「雑貨」の「貨」みたいな感じかな。ニュアンス的には
うーん、IOUはDingeなのかなぁ・・・
だってWie Eisen, Papier uswじゃないっすよね
Quantitätの側面、って事かなぁ
Geld だと抽象概念の「お金」、IOUは、個別に現れるものだから
もいっかい貼るね。

個別に現れる、ってのは、取引関係(これも御幣あるけど)それぞれで色んな形態をとってる、って事ですか?
こっちの「全」をIOUと呼んでます?
この一つ一つはみんなそれぞれIOUですよね
そうですね・・・ただ、nützliche Dingなのかな?って所がひっかかるんですよね
確かにnützliche Dingを得るためにnützlicheではあるんですけど・・・
これ読んでくれましたかね?
今読みましたw
ぎゃふん
たぶんここの個別の物と抽象化されたものとの関係は解ってる気がします。
で、お金と商品との関係がちょっとこんがらがってたんですけど、
マルクスのここの文章
ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache. Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d.h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel.
これからすると、いわゆる「商品」(日常言語的な意味での)じゃなくても、想像力から湧き出て何かのニーズを満たせばWareなわけか。
そして使用価値がゼロであっても「問題ではない」わけですよ。
流動性選好を考えてもいいけれど、それを仮定しなくても現実に交換はなされているわけで。
IOUがDingだとして、その次の Qualität と Quantität から検討されうるのかな?というのも引っかかってたんですけど
でも確かに貨幣と株式は質的に違うし
そうそう!
量的な分析も可能ではありますね。
はい、言葉が違う。これが「Qualität の違い」です。
あ、えーと
スプレッドシートが存在しない時代に、スプレッドシート的思考をしていたのがヘーゲルやマルクスなんですよ。
Qualtät =質的な検討も、 Quantität=量的な検討も可能ですね、って話でした
Ware ⊃ Ding (Qualität und Quantität)って感じなのねー
スプレッドシートで言うと、行が質、列が量という感じ。
Ding = das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt.
スプレッドシートの例えは解るような解らないような・・・
つかスプレッドシート=>表計算=>量的なものに引きずられそう
これ、何気に「doppelten Gesichtspunkt zu betrachten」ってのもポイントですかね?
めっちゃポイントです。
が、その前にですね
Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt.
Ware はまず、ein äußerer Gegenstand である
zunächst も結構おもいっすね
観念論の世界
認識論というか
あー
Gegenstand が Objectになっちゃう
これはちゃう感じ
あってます!!!
ただ、object も語源を考えれば ob-ject だから。。。
Gegen ・ Standだから
自分と相対する存在するなにがしか、って感じイメージかな
文の構造の話でもあるんですよね
subject – object 関係
んー
でもそうするとäußerer (外界の)ってつける意味は・・・?
Subject に対する Objectだとすると、äußerer って要ります??
うーん、なるほど
Ding は間主観的に表れていますよね。フッサール的に言うと
ein äußerer Gegenstand -> ein Ding, das durch seine…って運びになってるのがポイントか・・・
そうそう!
あのねーにゅんさん
これは伝わらないw
www
おじさんは哲学的な人だからなー
要するに物体的な意味でのObjectじゃなくて
主体の外側にあるObjectで、ひとつのDing、das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. って繋がりか
ですです
はいはい。
Ware(商品)はまず第一に自分の外側にある対象で、、、、ein Ding.
das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt….
あーめんどい
めんどいです
ドイツ語でわかれ!と言いたくなるw
Das Ding befriedigt durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art.
って事ですね、ここは・・・
楽しいなー
Das Ding が seine Eigenschaften をとおしてmenschliche Bedürfnisse を irgendeiner Art であれ befriedigt させる
めんどい!!
なるほど、ともあれこの特性に従えば貨幣もその特性をもってbefriedigen させるわけで、Ding でしかも主体の外にあるからWareで、つまりそれは資本主義社会における富として認識されうるWareの一部だと。
了解
\(^^)/
やっぱこれWare は商品じゃないなー
しいて言えば雑貨の貨かなー・・・一番感覚に近いのは・・・
じゃない、っていうか、わかりにくい・・・
このワーディングは経済学者やヘーゲルを踏まえているわけです。
労働が賃労働に引きずられちゃうようなもんで・・・・
Wareを商品って訳したのは合ってると思います??
ドイツ語で1語なのに2語にしたら意味変わりますよねぇ・・・?
そこは考えたけれど、「商品」しかないなあと。
言い換えるなら、総資産スプレッドシートの「項目」?みたいな。
ここは、やっぱ古典派の経済学者やヘーゲルの言葉を使わないと話が通らないんですよ。
まぁ、やたらと言い換える必要はないんですけど、日常言語と違うところはフォント変えるとか色変えるとかしないと誤解したまま突っ走りますね
特に商品と労働は2大誤読巨頭というか。
そうかもですね。
それまでの言論空間の中に資本論はあるわけで。
「ドイツ語の」ですよね
英語も含めていいと思います。
それを今のわれわれの感覚で単語を解釈してしまったら、意味がわかるわけがない。
でも・・英語もGegenstand が Object って出ちゃいますよ。。。対日本語より精度は高そうですけど
日本語はいい言葉なんですけどねー・・・
ともあれ、日本語のコンテキストに落とすにあたって、日常言語との用法の違いはビジュアル的にも解る方が良さげかなーって
だからいろいろ図を作りたいんです
ヘーゲルやマルクスは、イメージを印刷できなかったのだけど、今ならこうやっていたはず!みたいな表現が随所にあります。
そうですねぇ・・・
大事な試みだと思うんですよそういうの、すごく大事・・・
ただ、図解で示すことを知的に劣っているって解釈する向きが界隈には多そう
テキストは味が付きやすいって事がわかってる人めちゃ少ないですもんね・・
「言葉で(モデルで)論理的に説明できないとかwww」とか
そしてテキストを読み砕いていくのはひたすらめんどくさいし・・・
まぁその行きつく先が金ぴか本だったり妙なMMT本だったりするのかも

この大塚雄太先生良いこと言いますね
ほんとほんと
さて、すいません、深夜になってしまったので寝ます!!ありがとうございました。
こちらこそー
「ちゃんと」読むとはどういうことか
サイト開設のごあいさつを書きたいのだけど、言いたいことは第一回のマンガに尽きているかもしれない。
言いたいこと?
世界を変える
?
こんなふうに?
うっとり。。。
わんわん💛
だからみんなが資本論をちゃんと読めばいいと思う
MMTはそのあとかな
でもなんか難しそう。
共産主義のバイブル、みたいな?
うん、二年前に初めて読むまではそう思っていたのだけどさ。
(はずかしならが読もうとしたことがなかった)
そうなんだ
やっぱミッチェルと大石さん
言ってたね
ただ、上の写真に nyun がいないことに象徴されると思うけれど、MMTは「主流」ではない、
(犬だから?)
ミッチェルの言うことをいちばんわかっていたのは自分だとおもうけれど、マルクスは知らなかったんだよね。これはよい経験だったと思う。
ちょうどこの頃消費税が10パーセントに上がって、コロナがやってきて、総選挙があって、給付金がどうのとかやっているよね。
そうワンね
いまわれわれはこういう状態にあるわけだ。

そうだよねえ
賭けてもいいのだけれど、MMTの人たちが言っているJGP、つまり職業保証プログラムがスタートしない限り人びとの窮乏化は止まらない。
たとえ消費税が廃止されたり、反緊縮勢力が国会の絶対多数になったととしてもね。
そんな
今の日本の窮乏化の進行はほとんど完璧に資本論で論証されていて、その通りになっているという。
MMTがあるじゃないか
それだけが希望。
考え方を変えればいいんだよ、革命的に。
だからみんな資本論を読むべき (^^)/
そういうことか(^^)/
どうやって「ちゃんと」読むのか?
どんなふうにやるの?
普通に丁寧に読んでいこうということなのだけど、スタイルとしては逐文解釈的に。
有名な、冒頭の一文を見てみると。。。
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine “ungeheure Warensammlung”, die einzelne Ware als seine Elementarform.
(ドイツ語版)
英語版は、こう
The wealth of those societies in which the capitalist mode of production prevails, presents itself as an “immense accumulation of commodities”, its unit being a single commodity.
(英語版)
日本語への翻訳はいろいろあるけれど、たとえばこんなの。
資本家的生産様式が支配的である諸社会の富はひとつの‘巨大な商品の集まり’として現れ,個々の商品はかかる富の要素形態として現れる。
ふんふん
これはぜんぶ「感じ」が違う。
えー
特に日本語。
翻訳として間違っているということではなくて、思考の形が違うというか。
nyun がここで言ってた話ワンね

そうそう
ところで実は最近この動画にも感激しまして
アダムスミスは「経済学者」だったのか?の話
「アダムスミスは「経済学者」だったのか?」
大塚雄太先生
アダムスミスがこういうことを言う人だということを、普通の人は知っているだろうか?

大塚さんのご専門は、このへんだそうで

翻訳の歴史。。。
nyun の話と似てるワン
そしてここ。
レッシング!
シラー!

そのへんはわたくしもホームグラウンド\(^o^)/
そして!

古典を今の時代に生かそうということ。
それは世界を変えるということなんだよね。
nyunさん、これ動画の23分あたりなんだけど、そっくりなことやってるワン

そうなんだよ\(^o^)/


これを、マルクスでやろうということワンね
うん
ただね。
スミスの道徳感情論が出版された1759年から、マルクスの資本論の初版が出版された1867年の間には一世紀以上の開きがある。
ふんふんわんわん
上に出てきたレッシングからマルクスの哲学に至るまでにはゲーテとかカントとかシラーとかグリム兄弟とかフィヒテとかヘーゲルとか、それはそれは豪華絢爛な知の巨人が次々と現れた一世紀だったと思うんよ。
そしてナポレオンの登場や、フランス革命。
もう激動の時代。
そうワンね
nyun はもう何十年もこの時代のことを考えたり勉強してきたのだけれど、そういう基礎を土台にしてからマルクスを読み始めた犬ってめったにいないと思うんだよね。
読み書きができる犬がめったにいないワンね
そういう感覚で最初の文を読むと、いきなり何というか異様な雰囲気が漂っているわけ。
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine “ungeheure Warensammlung”, die einzelne Ware als seine Elementarform.
たとえば大学とかで講義するとして、これだけで半年持たせる自信あるくらい。
どのへんだろう?
Der Reichtum もだけれど、erschent als… と言う表現の精神現象学ぽさと、sammlung と einzelne という語の対比に現れる汎神論論争ぽさと、 Elementarform の Form の形態論ぽさ。
ヘーゲルとスピノザとゲーテが見える。
もちろん、経済学者たちもね。
そうなんだ!
だけど nyun が何言ってるかぜんぜんわからないでしょ?
わんわん
自分としても、かるちゃんともう一度丁寧に読んでいくことでその辺を確認していきたいわけ。
だからどうなるかはわからないし、決めない方がいいとも思う。
数年はかかるともうけれど、難解とされているらしい冒頭の「価値形態論」をあたりを一通りちゃんと読むことが当面の目標になります。
間に合うだろうか!
「 おお、親愛なるわが友、にゃん!」
なんかスイッチ入った?
「 早急に結論を出すのは控えよう。理想世界はいつか必ずやって来るのだから 」
格調高いな
「その時は必ず来るのだから、いつでも明るく勇敢に、言葉と行為で福音を伝えてくれ」
わんわん\(^o^)/
「死が訪れる、その日まで」
えええー
今の言葉はノヴァーリスだけど、結局のところ犬が幸福に生きるってのはそうことだよなあと。
わんわん